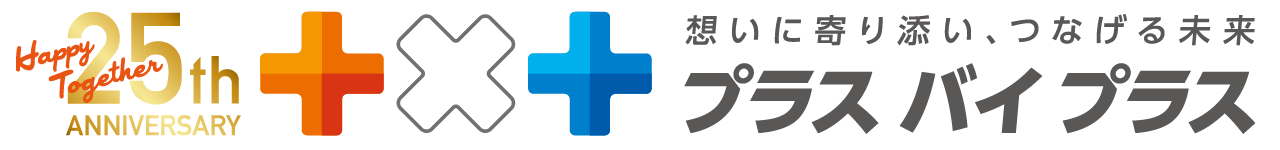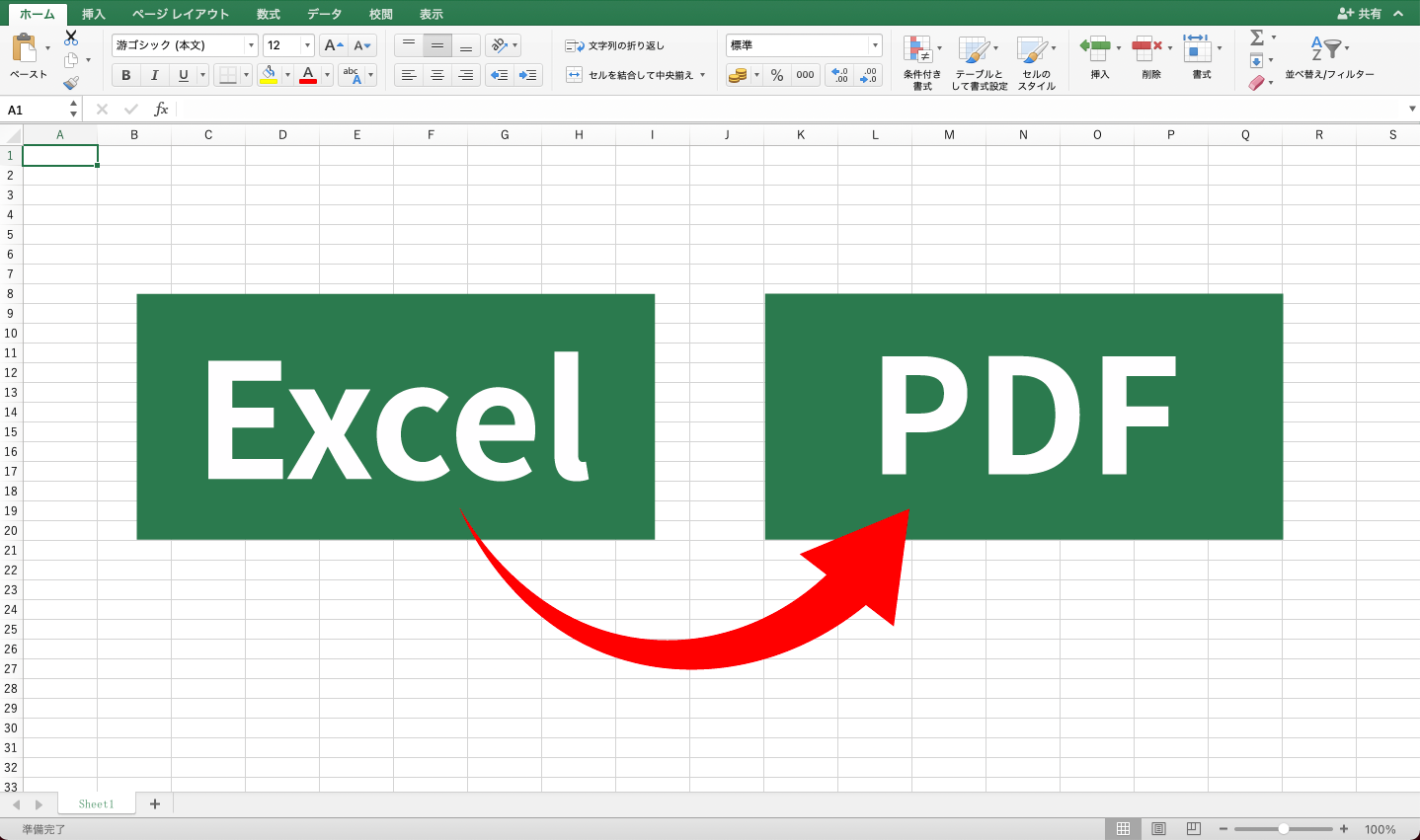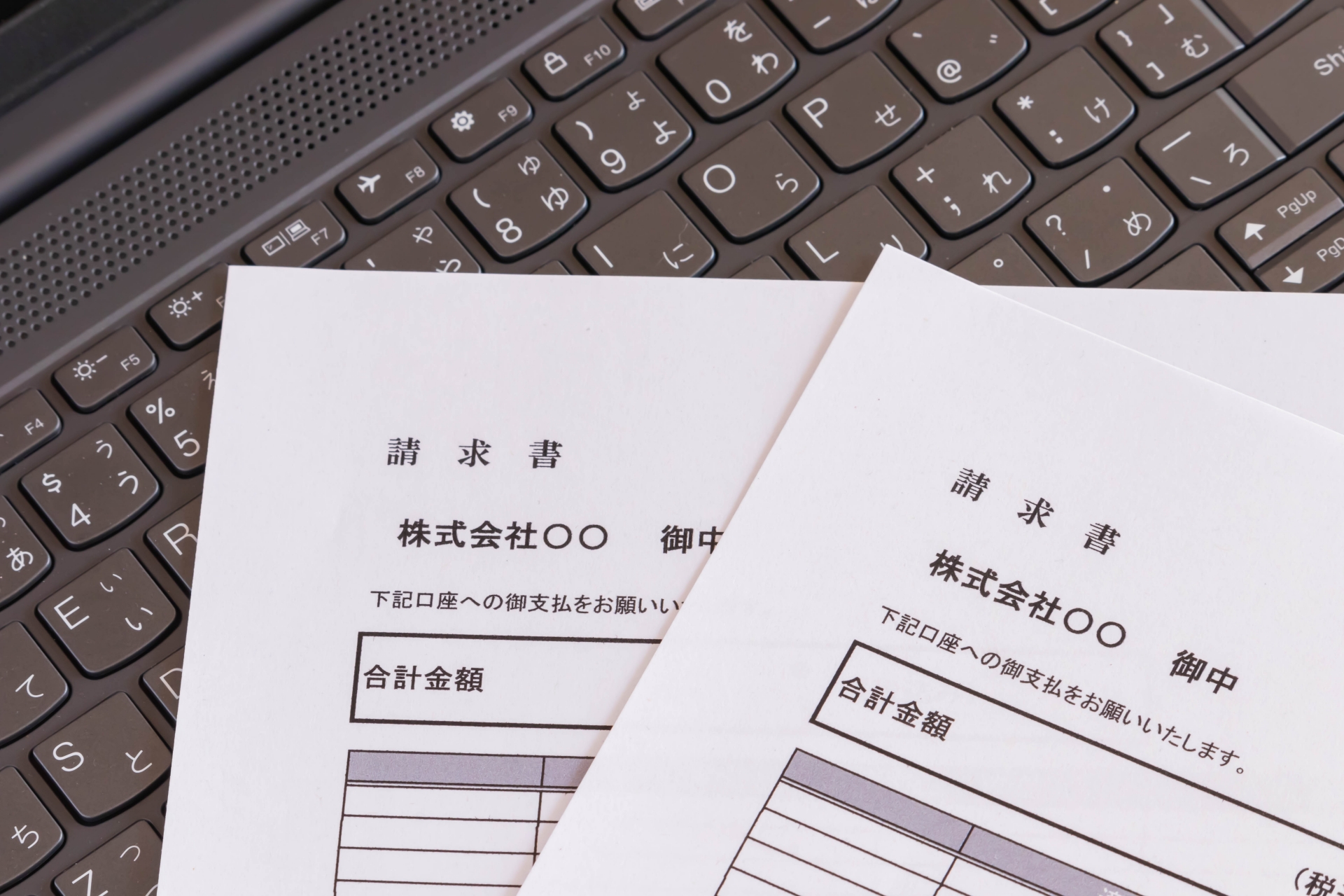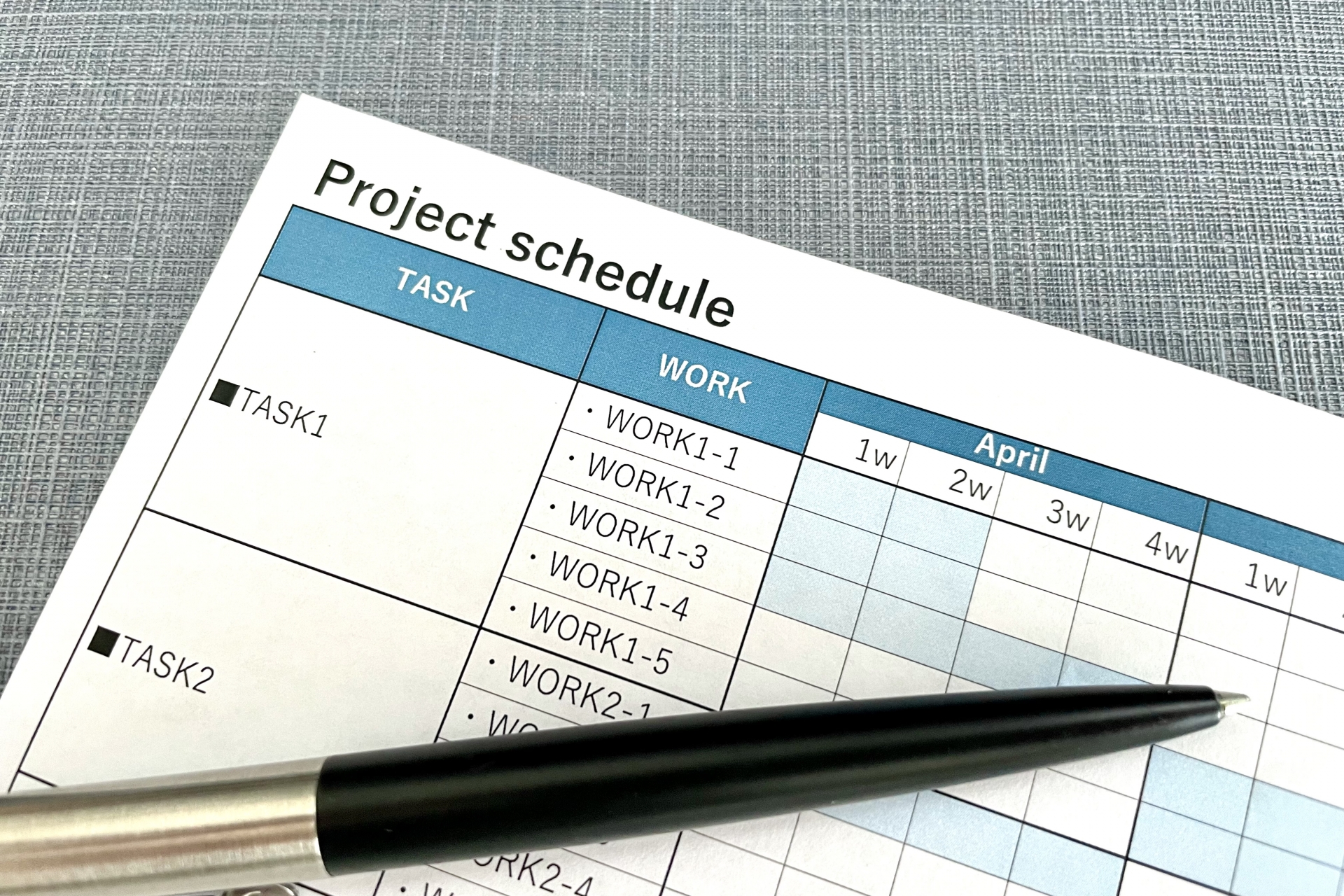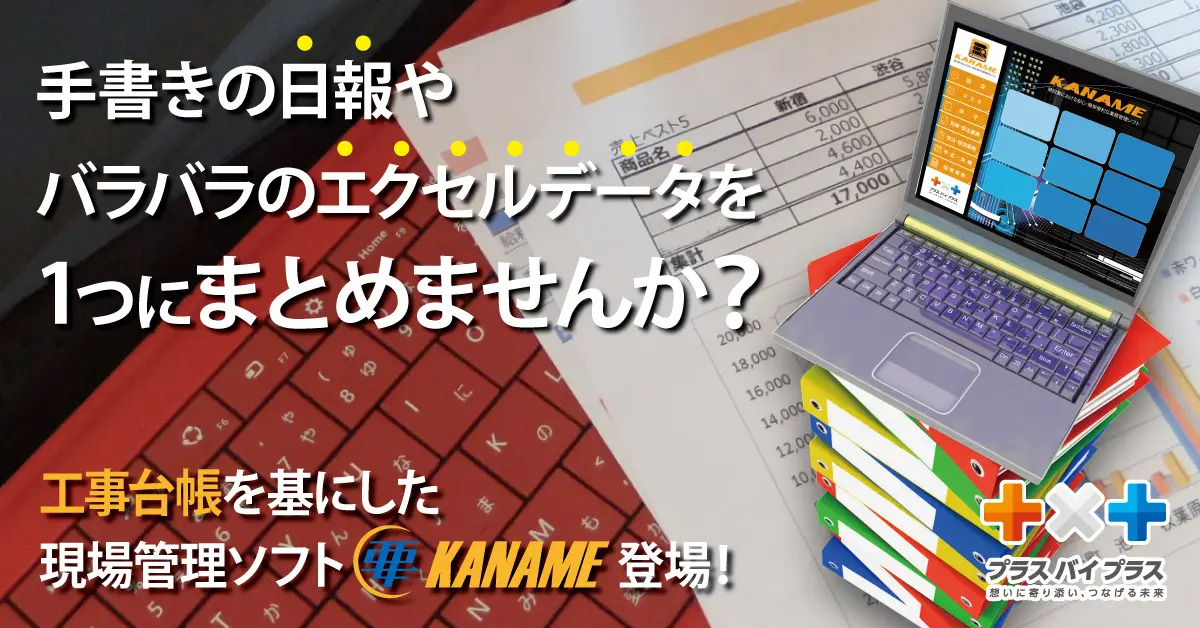- 2025年04月23日
建設業の実行予算とは?作成目的や内訳、原価との違いについてわかりやすく解説

建設業における実行予算とは、各工事ごとに現場で実際にかかる費用を詳細に見積り、効率的にコスト管理を行うための予算です。基本予算が計画段階で想定される大まかな費用を示すのに対し、実行予算は、より具体的かつ現実的な費用予測である点が大きな違いとなります。その目的は、工事の利益を確保するために材料費、労務費、経費などの各内訳を正確に算出し、コストコントロールを徹底することです。
実行予算の種類には、直接工事費や間接費などさまざまな項目があります。具体的な例としては、使用する資材の数量と単価を詳細に積算し、作業ごとの労務費や現場で発生する経費も網羅的に計上します。こうした費用の明確化によって工事実施中のコスト把握が容易になり、予定利益の達成や損失回避など経営判断の迅速化が可能になります。
実行予算の作り方では、図面や仕様書をもとに内訳明細書を作成し、各工程ごとにかかる費用を割り出します。また、工事進行中に発生した実績をもとに、必要に応じて予算の見直しや変更も行います。特に、予想外の追加工事や資材価格の変動が生じた場合は、実行予算を柔軟に修正することが重要です。
このように、実行予算は現場責任者の管理能力向上にも寄与しますし、工事全体の収益状況を正確に把握するためには不可欠なツールです。最終的には、基本予算や過去の実績と比較することで経営改善のヒントを得ることができ、持続的な利益確保や経営効率化につながります。
コンテンツ
建設業における実行予算とは
建設業における実行予算とは、各現場ごとの詳細な原価計画を作成し、工事の実態に即した正確な予算を算出するプロセスのことです。
実行予算とは、実際の作業に必要となる材料費や労務費、外注費、機械費などの各種経費を細かく積算し、工事全体の総費用を明確化する点で重要な意味を持ちます。見積書から導き出した概算金額を基に、現場特有の条件や状況を反映させて調整し、より現実的で具体的な予算へ落とし込むことが実行予算の特徴です。この過程では工期の変更や使用資材の選定など、状況の変化も考慮して適宜見直しや再調整が行われます。適切な実行予算の策定と管理は、工事の利益計画とコストコントロールの両立を可能とし、計画通りに現場運営を進めるための基盤となります。
実行予算と他の予算・見積りとの違い
建設業においては、実行予算や基本予算、見積りなど、複数の予算管理手法が存在し、それぞれの目的や使われる場面に違いがあります
実行予算と基本予算の違い
基本予算は会社全体の経営計画に基づいて年間や四半期単位で作成される予算で、主に経営層が企業全体の資金配分や戦略を決定する際に使用します。会社の売上や利益目標、投資計画など大枠を示すものであり、企業全体の経営方針や将来の方向性を明確にするために策定されます。一方、実行予算は具体的な工事現場単位や部門単位で作成され、材料費、労務費、機械費といったコスト項目を細かく把握し、現場ごとの実情に合った予算設定がなされます。実行予算は業務を行う現場担当者が日々のコスト管理や進捗管理を行う上で不可欠な役割を担っています。このように、基本予算と実行予算の違いは、前者が企業全体の大まかな予算枠組みであるのに対して、後者はより具体的かつ現場レベルに落とし込んだ詳細な計画となっている点です。それぞれの役割や目的を理解し、適切に活用することで、企業活動の効率化やコストの最適化が図れます。
実行予算と見積りの違い
見積りは工事を実施する前に発注元に提示するための金額で、積算した工事費用に会社の利益や管理費を加えた総額です。積算は、図面や仕様書から材料費や労務費、その他経費を詳細に計算し、見積りの基礎となります。一方、実行予算はこの見積り金額をもとにして、工事現場ごとに必要な原価を具体的な項目別に割り振り、各作業ごとに適切な予算を設定することで、効率的なコスト管理が可能になります。つまり、見積りが契約のための価格提示であるのに対し、実行予算は現場管理のための原価コントロールおよび進捗管理に役立つ内部資料であり、この違いをきちんと認識することが重要です。両者の違いを理解しておくことで、工事全体の収益状況や原価管理がより正確になり、無駄なコストを削減することが可能になります。
実行予算の作成目的
実行予算の目的は、工事現場ごとの費用を明確に把握し、効率的かつ無駄のない工事運営を実現することにあります。
利益の確保
実行予算の作成は、工事の利益を確保するために不可欠です。
見積時に設定される「見積原価」は概算であることが多く、実際の工事で発生する費用とは差が出ることがあります。そこで、施工段階に入る前に現実的な原価(材料費、労務費、外注費など)を精査し、「どこまで費用をかけて良いのか」を定めることで、利益を守る仕組みを作ります。
例えば、1億円で受注したビル工事において、見積原価が9,000万円だったとします。これを基に実行予算を作成し、「外注費は4,000万円以内、材料費は3,000万円以内」と細かく設定することで、予算内に収めれば1,000万円の利益が出る計算になります。これが明確になっていれば、現場でも無理な支出を避けやすくなります。
コストコントロールの指標
実行予算は、工事におけるコストコントロールの基準になります。
各費用項目ごとに予算を立てておけば、実際にかかった費用(実績原価)と比較して、コストがどこで膨らんでいるのかをすぐに把握できます。これにより、早期の対策が可能になります。
仮に、鉄筋工事の外注費に500万円の予算を設定していたが、途中で600万円かかる見込みが出た場合、現場では他の費用(たとえば仮設工事)を圧縮できるか検討したり、追加費用の根拠を精査することで、全体の収支を調整しやすくなります。
現場への指示・役割分担の明確化
実行予算は、現場担当者に対して明確な指示と目標を与える役割を持ちます。
現場で「どの項目にどれだけ費用をかけられるのか」が明確であれば、材料の発注判断や外注先への依頼などを、実行予算に照らして自律的に判断できます。
例えば、仮設工事に300万円の予算が割り当てられていれば、現場代理人は「仮囲いに200万円、足場に100万円までならOK」と判断でき、金額を超える提案が来た場合も、上長と相談の上で精査や見直しがしやすくなります。
発注・購買業務の最適化
実行予算は、外注先や仕入先との価格交渉や発注判断を適正化するための基準になります。
予算があることで「いくらまでなら出せるのか」が明確になり、適正価格での交渉が可能となります。無理な安値交渉ではなく、適切な価格帯での取引先選定も進めやすくなります。
例えば、コンクリートの打設工事に1,200万円の予算が設定されていれば、見積を複数社から取り、1,400万円提示の業者に対して「弊社の予算は1,200万円です。仕様を見直して収められませんか?」と交渉することで、コストの最適化を図れます。
社内報告・経営判断材料
実行予算は、工事の収支状況を経営層に報告し、事業の継続判断を行うための重要資料になります。
どの工事が黒字見込みで、どの工事が赤字リスクを抱えているかを把握することで、経営としてのリソース配分(人員・資金)や受注戦略に反映させることができます。
例えば、同時進行している5件の工事のうち、2件が実行予算比で著しくオーバーしているとわかった場合、他の黒字工事でカバーできるかを検討したり、問題のある現場に指導員を追加派遣するなどの経営判断が可能になります。
建設業における実行予算の内訳
実行予算は、工事現場で必要となるさまざまな経費の種類を細かく分類し、それぞれの内訳を明確にしたうえで積み上げて組み立てられます。これにより現場ごとに実際の支出を正確に予測しやすく、効率的なコストコントロールが実現できます。経費は主に材料費、労務費、外注費、機械費、さらに現場経費などの種類に分けられており、それぞれの内訳と予算全体への比率を正確に把握することが、予算管理の基本となります。
| 項目名 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 材料費(資材費) | 建設に必要な建材や資材の購入費用 | 鉄筋、コンクリート、木材、断熱材、塗料、配管・配線資材など |
| 外注費(下請費) | 専門工事業者や下請業者への発注費用 | 基礎工事、内装工事、電気・空調・衛生設備工事など |
| 労務費(直用労務費) | 自社作業員や職人の人件費 | 自社社員の日当、アルバイトの賃金など |
| 重機・機械使用料 | 建設機械・重機のレンタル費や使用に伴う費用 | クレーン、バックホウ、高所作業車のレンタル、燃料代、オペレーター費用など |
| 仮設費 | 工事に必要な一時的な設備・構造物にかかる費用 | 足場、仮囲い、仮設トイレ、現場事務所の設営・撤去費用など |
| 諸経費(現場経費など) | 工事現場の運営・管理にかかる共通的な費用 | 現場監督の人件費、交通費、通信費、安全対策費、保険料など |
| 一般管理費 | 本社で発生し工事に配分される間接的な費用(※会社方針による) | 本社社員の人件費、社内システム使用料、営業活動にかかる経費など |
実行予算と実際にかかった費用の比較と見直し
建設業においては、実行予算と実績の比較・見直しを定期的に行うことで、工事の収益性を守り、経営上の意思決定を迅速かつ的確に行うことができます。
実行予算は工事着手前に立てる「目標となるコスト計画」であり、実績は現場で実際に発生した費用です。これらを継続的に比較することで、予算からの乖離(差異)を発見でき、原因を分析することで工事途中のリスクに対して早期の対応が可能になります。特に長期にわたる案件や多工種が絡む案件では、工程中の見直しが収支結果に大きな影響を与えます。
比較・見直しのメリット
・コストの異常(オーバーや未消化)を早期に把握できる
・原因分析によって、今後の支出や工程を調整しやすくなる
・工事中の収益性がリアルタイムに管理できる
・経営層への報告資料として活用でき、経営判断を迅速化できる
・次回以降の実行予算や見積精度の向上につながる
見直しの流れ
STEP1:定期集計
月次や工程節目で、各費目(材料費・外注費・労務費など)の「実行予算」と「実績金額」を一覧で集計します。
STEP2:差異分析
金額差や割合差を算出し、乖離の大きい項目をピックアップします。
STEP3:原因特定
発注ミス・仕様変更・単価の変動・作業手戻りなど、差異が生じた原因を現場担当者や管理者とともに確認します。
STEP4:是正・調整対応
残り工程でのコスト圧縮、仕入先見直し、外注範囲の再検討などの対応を検討・実施します。
STEP5:再予算・報告
必要に応じて実行予算を再設定し、関係者間で共有。月次報告資料や社内会議で進捗と対策を説明します。
この流れを継続的に繰り返すことで、現場主導のコスト管理が可能になり、ひいては会社全体の利益体質の強化にもつながります。
まとめ
実行予算の精度が高い会社は、「見積りに根拠がある=工事金額に対する説得力がある」ため、発注者や協力業者に対して高い信頼感を与え、長期的な取引関係の構築につながります。
発注者(施主・元請け)や協力会社にとって、「どんぶり勘定の見積り」よりも「過去の実績や根拠に基づいた見積り」の方が安心感があります。工事費が高くても、「なぜこの金額なのか」が説明できれば納得されやすくなり、値引き交渉にも一定の歯止めがかかります。
また、多少金額が他社より高くても、「信頼できるからこの会社に任せよう」となるケースはよくあります。
確実に実行予算を作成し、利益率アップ・社外の信頼の獲得を目指しましょう。
何から始めたら良いかわからないと思ったら専門ソフトの導入がおすすめ
実行予算の作成は確実性が求められる作業のため、経験がない方が行うにはかなりハードルが高いものです。
それでも、もっと利益を確保して会社を安定させたい、取引先に出す数字に根拠を持たせたいという場合は、専門ソフトの導入を検討してみても良いかもしれません。
建設業向け原価管理システム「要 〜KANAME〜」は、案件ごとの数字を一元管理して経営改善を行うための機能が揃っていることはもちろん、お客様のやりたいことを実現するために専任担当者による運用サポート体制が整っています。
お客様レビュー:漠然と数字を管理しないといけない状態から利益が2〜3倍に
株式会社ケイズエアシステム様は、社員が増えていく中で、現場ごとの予算や労務費を管理しなければならないと漠然と考えいた状態から、利益が2~3倍に増加しました。これは、「要 ~KANAME~」で利益管理を行ったことで、リアルタイムで利益を可視化できるようになったことが大きな要因です。
具体的には、どの現場が利益を生み出しているか、どこに無駄があるかをすぐに把握できるようになり、そのデータを基に効率的な施策を講じることができました。これにより、無駄なコストが削減され、利益を最大化することができたのです。
また、これまで月単位で管理していた経営状況が、日々の進捗を管理するシステムによって、瞬時に確認できるようになりました。このようなシステム導入により、従業員が自ら利益向上に向けた行動を意識的に取るようになり、利益率が大幅に向上しました。