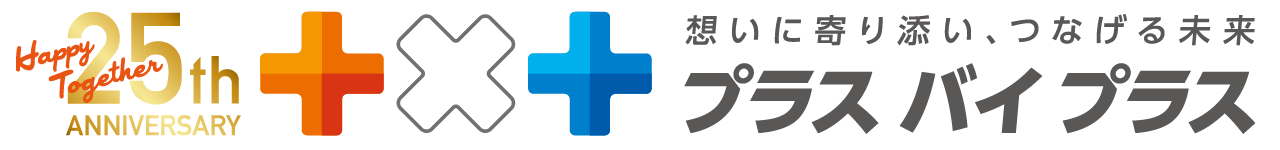- 2025年04月01日
建設業は儲からない?原因を徹底分析し、高収益体質へ転換しよう

建設業界に従事する企業や経営者のなかで、「建設業は儲からない」と頭を悩ませる方もいるでしょう。建設業界が抱える多くの課題は、非常に深刻であり、経営者にとってその改善が急務となっています。特に、低利益の状態が続いている場合、企業の持続的な成長は難しく、競争力を維持することも困難になります。しかし、建設業が儲からない原因をきちんと理解し、適切な対策を講じることで、高収益体質へと転換することは十分に可能です。
この記事では、建設業界が直面している課題や原因、それに対する改善策について解説します。
コンテンツ
建設業が儲からない原因
建設業が儲からない原因として、以下のような点があげられます。
価格競争の激化
近年、建設業界は価格競争の激化に悩まされています。多くの建設業者が受注を取るために、価格を引き下げる状況が続いています。これが進むと、競争が過度に厳しくなり、利益率がどんどん圧縮されていきます。特に中小の建設業者にとって、価格競争は致命的な要因となりやすく、工事ごとの単価が安くなりすぎると、企業の運営自体が難しくなってしまうのです。
建設業界では、原材料や人件費などが高騰するなかで、価格を下げて工事を受注することが求められる場合があります。そのため、仕事を受注するために低価格で受注を重ねることが、「儲からない」という状況を加速させてしまうのです。特に、競争が過熱している地域では、業者同士の過剰な価格引き下げが進み、結果として収益が低下するケースが増えています。
下請け構造
日本の建設業界において、下請け構造は長年の慣習となっています。この下請け構造も、建設業が「儲からない」と考えられる要因の一つです。元請けと下請けという二重構造が続いているなかで、下請け業者は元請け業者に対して常に価格面で圧力を受けることが多く、利益を確保することが難しくなります。下請け業者の立場では、受注する工事に対して十分な利益を得ることができず、結果的に「儲からない」という状況に陥りやすいです。
また、下請け業者は元請けからの要求に応じなければならないため、工事にかかる時間や労力を効率的に削減することが難しく、利益率を高める余地が少なくなります。このような構造が続くことで、業界全体として儲かりづらい状況が続いています。
人件費の高騰
建設業界の人件費は年々上昇しており、特に熟練した技術者や職人の人材不足が深刻です。建設業は非常に労働集約型の産業であり、多くの人手を必要とするため、人件費の高騰は企業の利益に大きな影響を与えます。若年層の労働者が不足している現状では、高齢化が進む現場において、若手職人を採用し育てるために高額な賃金を支払わざるを得ないという事態に陥っています。
このような人件費の高騰は、企業の運営コストを押し上げ、利益を圧迫します。企業が十分な利益を確保する前に労働者への支払いや福利厚生などにお金を使うことになるため、収益を上げるのが難しくなります。
原材料費の高騰
建設業における原材料費の高騰も、儲からない原因として大きな要因となっています。鉄鋼やコンクリート、木材などの建設資材は、供給不足や世界的な需要の高まりなどにより、価格が上昇しています。この原材料費の高騰が、建設業者にとって大きな負担となり、利益率を低下させているのです。
原材料費の上昇は、工事の価格に直接的に影響を与えます。一方で、顧客も価格を重視する傾向が強いなか、原材料費が上昇しているにもかかわらず価格を下げざるを得ない場合、利益を圧迫し、儲からない状況に陥ってしまいます。
技術革新への対応の遅れ
建設業界は、他の産業と比べて技術革新の導入が遅れているとされています。新しい技術や自動化システム、ITを駆使した現場管理など、効率化や品質向上のための技術革新は、今後の競争において重要な要素です。しかし、伝統的な手法を重視し、変化に対して抵抗感をもつ企業は、効率化やコスト削減に遅れをとっているのです。
IT技術や自動化技術を活用しない企業は、どうしても他社と比べて労働力や時間に依存した運営をしてしまいます。そのため、業務効率の改善が進まず、利益率が低いままの状況が続いてしまうのです。
業務効率が悪い
建設業界では、業務効率が悪いと感じている経営者が多いです。現場の進捗管理や資料作成、工事の手配などが手作業で行われることが多く、時間がかかり、無駄が多く発生します。プロジェクト管理のツールが十分に活用されていない場合、情報の共有が遅れたり、ミスが発生したりすることもあるでしょう。
非効率な状態が続くと、無駄なコストが発生し、最終的には企業の利益を圧迫することになります。業務効率化を図るためには、デジタルツールの導入や現場管理システムの整備が求められます。
原価管理が甘い
建設業者が儲からない原因の一つに、原価管理が不十分なことがあります。特に、工事のコストを正確に把握せずに進めると、最終的にコストオーバーとなり、なかなか予定していた利益を確保できません。原価管理が不十分な場合、予算を超える費用が発生し、その分利益が削られてしまうことになります。
原価管理は建設業において非常に重要な要素であり、工事ごとのコストをしっかりと管理することが、利益を確保するために欠かせません。
資金繰りの悪化
建設業は、特に大型の工事を行う場合、長期間にわたる工期を必要とするため、資金繰りの問題が発生しやすくなります。工事の途中での支払いが遅れたり、材料費が急激に上昇したりすると運転資金が不足し、資金繰りが悪化すると、事業の運営に支障が生じ、最終的には利益を上げることが難しくなってしまうのです。
人材不足
建設業界では、若年層の人材不足が深刻です。特に職人や技術者といった専門的な人材の確保が難しくなっています。若い世代の人材確保が難しく、人口減少や少子化の影響を受けている業界です。人材不足が続けば、現場作業が進まないことや、質の高い工事を提供できなくなることがあります。
労働力の高齢化
建設業界は、労働力の高齢化が進んでいます。特に現場作業を行う職人や技術者の多くが高齢者となり、引退する年齢に達しています。若年層の採用が進まないなかで、高齢者が現場に多く残っている状況が続くと、効率よく作業を進めることが難しくなり、結果的に利益率が低くなってしまうのです。
利益を上げるための具体的な戦略
建設業が直面している「儲からない」という問題に対しては、さまざまな戦略を講じることが可能です。以下のような戦略をうまく取り入れることで、収益性を高め、より安定した経営基盤を構築することが可能です。
高付加価値化
建設業界では、価格競争を避けるために、単に安価なサービスを提供するのではなく、付加価値を提供することが非常に重要です。高付加価値の提供とは、品質やデザイン性、技術力など、他社と差別化できる要素を強化することです。たとえば、エコ建築や省エネ設備、デザイン性に優れた建物など、顧客のニーズに応じた価値を提供することで、単価を上げることができます。
差別化戦略
他の企業と同じようなサービスを提供していては、競争に勝つことはできません。したがって、差別化戦略が不可欠です。差別化とは、提供する商品やサービスが他社とは異なる特徴や価値を持つことを意味します。たとえば、建設業であれば、特定の地域に特化したサービスや、特定のニーズに対応する専門的な工事を提供することで、他社と一線を画すことができます。
また、近年注目されているのが「環境配慮型建設」です。持続可能性やエコロジーに配慮した建物を提供することで、環境意識の高い顧客をターゲットにした差別化が可能です。こうした差別化を図ることで、高い価格帯でも十分に受注を得ることができます。
直接受注の増加
建設業界では、下請けの仕事が強いと利益が少なくなることがあります。直接受注を増やすことは、利益率を向上させるために重要です。特に、顧客との直接契約により、無駄な中間マージンを省くことができます。
直接受注を増やすためには、企業の信頼性やブランド力を高め、マーケティング活動を強化する必要があります。顧客にとって信頼のおける企業であることをアピールし、安定した取引先を確保することが求められます。また、直接受注に向けて営業活動を強化し、地域密着型での営業活動を行うことも有効です。
業務効率化
業務効率化は、建設業の収益性向上に欠かせない要素です。現場での作業効率を向上させるためには、最新の建設技術を取り入れたり、プロジェクト管理のデジタル化を進めたりすることが重要です。特に、ITツールや建設業向けの専門ソフトウェアを導入することで、現場作業の進捗管理や資材調達、コスト管理を効率化できます。
また、効率化のためには、作業員の役割分担や作業フローの見直しを行うことも有効です。無駄な作業や重複作業を減らすことで、コストを削減し、利益を確保することができます。
コスト削減
建設業においてコスト削減は非常に重要なポイントです。コスト削減を実現するためには、資材費や人件費、その他の運営費用を細かく見直し、削減できる部分を洗い出す必要があります。たとえば、長期的に安定した取引先との関係を築き、資材の仕入れ単価を下げることや、効率的な人員配置を行うことでコストを抑えることが可能です。
また、過剰な設備投資や不要な支出を抑えることも重要です。経営資源を効率的に活用し、必要な投資のみを行うことで、無駄なコストを削減することができます。
人材育成
建設業界の最大の資産は人材です。特に熟練した技術者や職人が不足している現代において、優秀な人材を育成することは企業の競争力を高めるために欠かせません。人材育成には、定期的な研修や技術講習の実施、キャリアパスの提供が含まれます。また、若手社員に対しては、早い段階から責任ある業務を任せて成長を促進することが重要です。
人材育成をしっかりと行うことで、現場での作業品質や効率が向上し、結果的に企業の収益性を向上させることができます。さらに、優秀な社員が定着することで、企業のブランド力が高まり、顧客からの信頼を得ることができます。
新規事業
建設業界の成長には、新規事業の開拓も重要です。例えば、既存の建設業務に加えて、リフォームや修繕、インフラ整備などの関連事業に進出でき、収益の多角化を図れます。
また、新たな事業として、環境関連の事業に進出することも一つの戦略です。今後、環境に配慮した建設や再生可能エネルギーを利用した建築などが重要になってくるため、この分野に注力することが企業の成長に繋がります。
M&A(合併・買収)
M&A(合併・買収)は、建設業界においても有力な戦略です。競争が激化しているなかで、他社と統合することで、規模の経済を実現し、コスト削減を図ることができます。特に、規模が小さい企業やリソースが不足している企業が、大手企業と統合することで、より多くの受注を確保することが可能となります。
M&Aを活用することで、技術力や営業力の向上が期待できるほか、新しい市場に進出することもできます。M&Aを成功させるためには、企業の文化や戦略をうまく統合することが重要です。
海外展開
国内市場が成熟しているなかで、海外展開を視野に入れることも有効です。特に、アジアや中東地域など、建設業が成長している市場に進出することで、新たな収益源を確保することができます。海外市場に進出すれば国内の景気の影響を受けにくくなり、安定した収益基盤を作ることができるでしょう。
海外展開を行う際には、現地の文化や法律、商習慣を理解し、現地パートナーと協力することが重要です。戦略的に進出先を選定し、リスクを最小限に抑えながら事業を展開することが求められます。
補助金・助成金活用
建設業者が利用できる補助金や助成金は数多く存在します。特に、環境に配慮した建設や、省エネルギー対策を行う場合には、政府や自治体からの支援を受けることが可能です。これらの支援を上手に活用することで、初期投資を抑え、事業の立ち上げをスムーズに進めることができます。
まとめ
建設業が儲からない原因は、価格競争、下請け構造、コストの高騰、技術革新の遅れなど、さまざまな要因が絡み合っています。しかし、これらの課題に対しては、戦略的な対応を取ることで、高収益体質への転換が可能です。高付加価値化や差別化、業務効率化などを進め、収益性を向上させるための具体的な戦略を実行することが、今後の成長に繋がります。
利益をきっちり出すには素早い経営判断が大切
利益を出すためには、原価管理を徹底することが重要です。
ただし、建設業の業務フローや資金繰りは他業種と比べて特殊で複雑なため、細かく全てを管理しようとするとかなりの労力がかかります。
そのため、確実に管理して利益を出していくなら専門の原価管理ソフトの導入を検討してみても良いかもしれません。
建設業向け原価管理システム「要 〜KANAME〜」なら
・工事台帳に情報を集約し一元管理!
・工事ごとの収支をリアルタイムに把握!
・労務費は日報から自動で人工計算!
・作成した見積や注文書を一覧で視える化
など、「会社の今」を見て迅速な経営判断を行うことが可能になります。
建設業の売上向上についてよくある質問
建設業界で利益を上げるためには、まず何から始めれば良いですか?
建設業界で利益を上げるためには、まず現状の問題点をしっかりと分析し、改善するところから始めることが大切です。最も重要な第一歩は「コスト管理」と「業務効率化」の見直しです。これらは収益に直結する要素で、無駄なコストを削減し、業務の進行をスムーズにすることが、短期的に見ても長期的に見ても非常に効果的です。
具体的には、以下のような点に注意が必要です。
- 原価管理の徹底: 施工現場での材料費や労務費の管理をしっかり行い、過剰な支出を避ける。
- 業務のデジタル化・IT化: プロジェクト管理ソフトや現場監督ツールを導入し、作業の進捗やコストをリアルタイムで把握する。
- 無駄な人件費の削減: 過剰な人員配置や無駄な作業を見直し、最適な配置を行うこと。
これらを徹底することで、まずはコストを抑制し、利益を出しやすくする基盤を作ることができます。
新規事業を始める際に注意すべき点は?
新規事業を開始する際の最も大切な点は、市場調査とターゲット設定です。新たに進出する事業領域がどれだけ成長性があり、競争が激しいのかをよく分析することが成功への第一歩です。また、事業を展開する際は以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 市場調査: 新しい事業分野に対する市場の需要をしっかりと調査し、その分野にどれだけの競合がいるか、またその競合との差別化ポイントは何かを把握します。
- ターゲット層の明確化: 自社の提供する商品やサービスがどのような顧客層に向いているのかを明確にし、そのニーズに対応できるような製品・サービスを設計します。
- 初期投資の検討: 新規事業には一定の初期投資が必要ですが、その回収見込みや収益化までの時間を慎重に見積もることが大切です。
- リスク管理: 新規事業には不確実性が伴います。従ってリスクを最小限に抑えるために、複数のシナリオを描いて準備しておくことが重要です。
さらに、建設業界においては、環境配慮型の事業やリノベーション事業など、成長分野に積極的に参入することが有望です。新たな事業に取り組む際には、常に市場の動向を注視し、柔軟に対応する姿勢が求められます。
価格競争から抜け出すために何をすべきですか?
建設業界では、特に価格競争が激化しているため、単に安価なサービスを提供するだけでは利益を上げることが難しくなります。価格競争から抜け出すためには、他社と差別化できる要素を見つけ、その点を強調することが非常に重要です。以下の方法で差別化を図ることが可能です。
- 付加価値を提供する: ただの建設工事ではなく、デザイン性の高い建築や、省エネ・エコロジーに配慮した建物を提供することで、顧客の関心を引き、価格以外の部分で競争力を高めることができます。
- 特化した専門性を持つ: 建設業界のなかでも特定の分野(例えば、耐震・免震構造に特化した建設)で専門性を高めることで、他社と差別化し、高い価格でも顧客に選ばれることができます。
- 顧客サービスの強化: 工事の後も顧客との関係を築き、アフターサービスや定期的なメンテナンスを提供することも顧客の満足度を高める要素となります。
差別化戦略をうまく打ち出すことで、価格競争に巻き込まれることなく、利益を確保することが可能です。
海外市場に進出する場合、どのような準備が必要ですか?
国内市場の競争が激化するなか、海外市場への進出は有力な成長戦略となります。特に、アジアや中東などの新興市場では、建設業の需要が高まっており、進出のチャンスが広がっています。しかし、海外市場に進出するには慎重に準備を進める必要があります。以下は進出に際して注意すべき点です:
- 現地の市場調査: 進出先の市場で建設業に対する需要や競争の状況をしっかりと把握することが重要です。また、現地の文化や商習慣を理解することも大切です。
- 規制や法律の確認: 各国には建設業に関する独自の法律や規制が存在するため、現地の法規制を十分に調査し、適切な許認可を取得することが必要です。
- 現地パートナーの選定: 進出先で信頼できる現地企業とのパートナーシップを結ぶことが成功のカギを握ります。現地の事情に精通している企業と協力することで、スムーズな進出が可能となります。
- 資金計画とリスク管理: 海外市場への進出には大きな投資が必要です。資金の調達方法やリスクヘッジについて、事前に計画を立てることが重要です。
海外展開はリスクもありますが、慎重に進めることで大きな利益を得ることができる可能性があります。
人材不足の解決方法として、どのような取り組みが効果的ですか?
建設業界では、特に技能を持つ職人や技術者が不足しているという課題があります。人材不足を解決するためには、短期的・長期的な取り組みが必要です。具体的には、以下のような方法があります:
- 若手の採用・育成: 新しい人材を積極的に採用し、教育・研修を通じてスキルを身につけさせることが重要です。また、職場でのキャリアパスを明確にし、若手社員が将来的にどのように成長できるかを示すことが、採用活動の魅力につながります。
- 労働環境の改善: 建設業界は過酷な作業環境であることが多いため、作業環境の改善や福利厚生の充実を図ることが重要です。柔軟な働き方や作業時間の見直しを行うことで、従業員の定着率が高まります。
- 女性や高齢者の活用: 労働力の多様化を進めることも一つの方法です。女性や高齢者が活躍できるような作業環境を整えることで、労働力を確保することができます。
- 技術革新を活用: 人手不足を補うために、建設現場でのロボット技術やドローン、AIなどの新技術を導入することで、作業効率を上げ、少ない人員でも高い生産性を維持することが可能です。