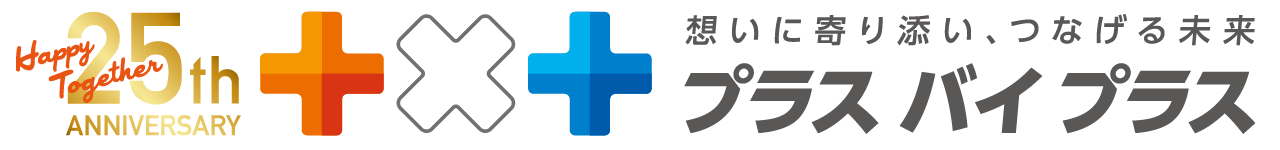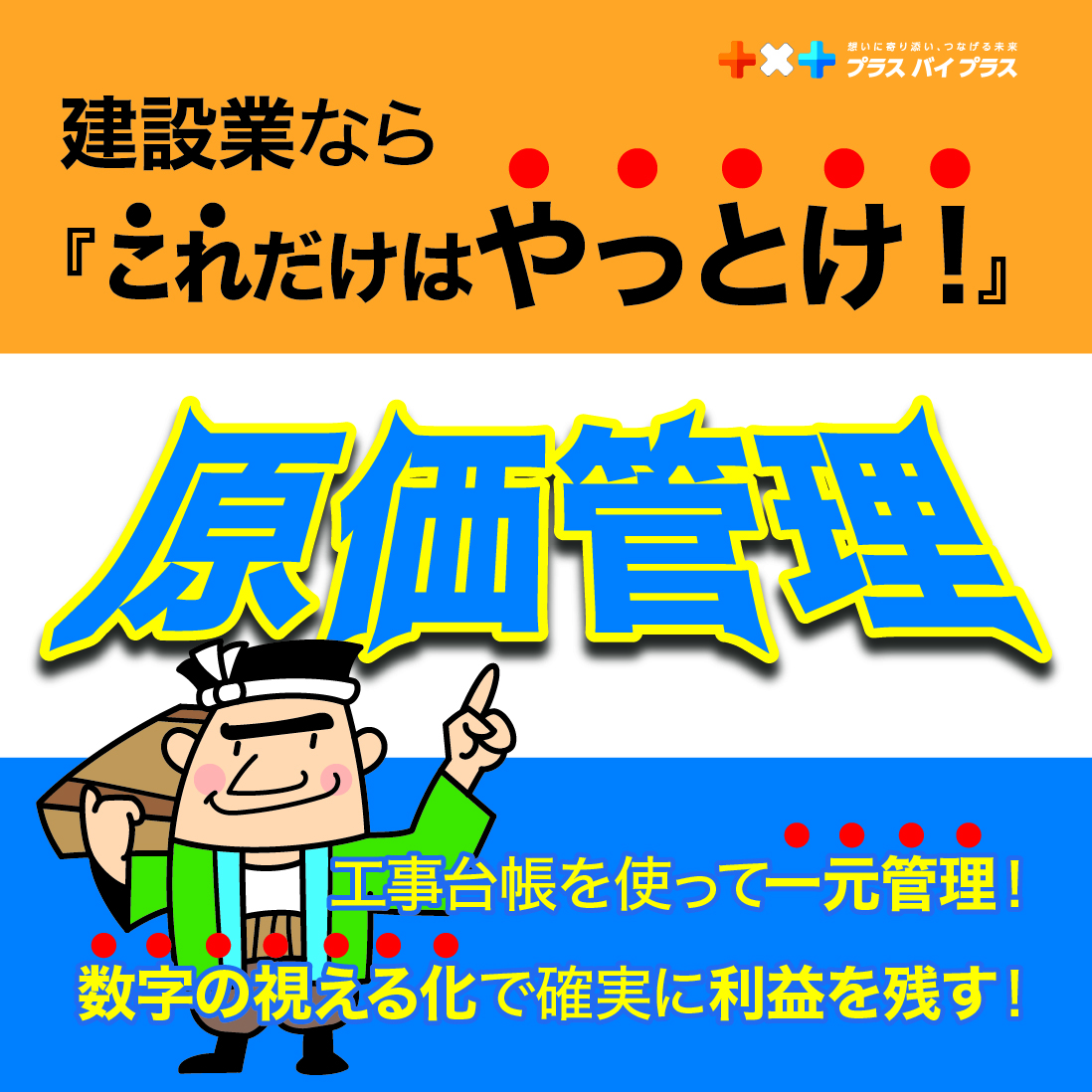- 2025年04月01日
建設業向け利益管理ソフトの導入費用はどれくらい?選び方とコストを抑える秘策

建設業の経営者にとって、利益の最大化は最重要課題の一つです。そのためには、日々の工事における収支を正確に把握し、戦略的な経営判断を行うことが不可欠です。その強力なツールとなるのが、利益管理ソフトです。
本コラムでは、利益管理ソフト導入のメリットから、費用の内訳、相場、コストを抑えるためのポイント、そして選び方まで解説します。利益管理ソフトの導入は、単なるコストではなく、未来への投資です。適切なソフトを選び、賢く活用することで、業務効率化、コスト削減、そして利益率向上を実現しましょう。
コンテンツ
利益管理ソフトを導入するメリット
利益管理ソフトの導入は、建設業の経営において以下のようなメリットが期待できます。
正確な原価計算
建設業において、正確な原価計算は利益管理の基礎となるものです。利益管理ソフトを導入することで、これまでExcelなどで行っていた煩雑な原価計算を自動化し、正確かつ迅速に利益管理ができます。
労務費、材料費、外注費などのコストを正確に把握し、各プロジェクトにかかった費用を項目ごとに詳細に管理したり、事務所の家賃や光熱費など、間接費を各プロジェクトに適切に振り分けたり、変動費と固定費を区別し、損益分岐点を把握したりすることが可能になります。
これらの情報に基づいて、より正確な利益を把握し、経営判断に役立てることができるでしょう。
見積り精度向上
正確な原価計算に基づいて、より精度の高い見積りを作成することができます。過去の類似案件の原価データに基づいて見積りを作成したり、最新の単価情報に基づいて自動で見積りを計算したり、リスク要因を考慮した見積りを作成したりすることが可能です。
これらの機能により、見積りの精度が向上し、利益を確保できる適正な価格で受注できるようになります。
収益性分析
利益管理ソフトを活用することで、工事ごとの収益性分析が容易になります。各工事の売上、原価、利益を詳細に分析し、利益率の高い工事、低い工事を明確に把握することができます。
その結果、利益率の高い工事に注力したり、利益率の低い工事の改善策を検討したりするなど、より戦略的な経営判断を行うことが可能になります。
コスト削減
利益管理ソフトは、間接的なコスト削減にも貢献します。例えば、書類作成や集計作業などの事務作業を効率化することで、人件費を削減できます。
また、材料費の管理を適切に行うことで、無駄な発注や在庫管理のミスを防ぎ、材料費の削減にも繋がります。
経営判断の迅速化
利益管理ソフトを活用することで、経営状況をリアルタイムで把握し、迅速な経営判断が可能になります。
売上、利益、キャッシュフローなどの経営指標をリアルタイムで把握したり、異常値を早期に発見し、迅速な対応を促したり、経営状況に基づいた迅速な意思決定をサポートしたりすることが可能に。変化の激しい建設業界において、迅速な経営判断は非常に重要です。
キャッシュフロー改善
利益管理ソフトは、キャッシュフローの改善にも役立ちます。正確な原価計算に基づいた請求書作成や、入金管理の効率化により、資金繰りの改善に繋がります。また、未回収金の早期把握や、支払い期限の管理なども、キャッシュフローを安定させるために重要です。
利益管理ソフト導入費用の内訳
利益管理ソフトを導入する際には、さまざまな費用が発生します。費用の内訳を理解し、予算計画を立てることが重要です。建設業向け利益管理ソフトの導入費用は、大きく以下の3つに分類できます。
初期費用
初期費用は、ソフトの導入時に一度だけ発生する費用のことで、以下のようなものがあげられます。
・ソフト本体の購入費用(ソフトのライセンス費用や買取費用)
・導入支援費用(ソフトの設定、操作指導、データ移行などのサポート費用)
・カスタマイズ費用(自社の業務に合わせてソフトをカスタマイズする場合の費用)
ハードウェア費用(サーバーやパソコンなどのハードウェアを新たに購入する場合の費用)などが含まれます。
初期費用は、ソフトの種類や規模、導入支援の内容によって大きく異なります。
ランニングコスト
ランニングコストとは、ソフトの利用期間中に継続的に発生する費用のことで、以下のような内容です。
・月額利用料
・保守費用(ソフトのアップデートやサポートを受けるための費用)
・サーバー費用(自社でサーバーを運用する場合の費用)
ランニングコストは、ソフトの種類や契約形態によって異なります。
その他費用
上記以外にも、以下のような費用がかかる場合があります。
・バージョンアップ費用(ソフトのバージョンアップを行う場合の費用)
・追加ライセンス費用(利用ユーザー数を増やす場合の費用)
・データ移行費用(既存のデータを新しいソフトに移行する場合の費用)
・教育費用(社員向けの研修費用)
これらの費用も考慮して、トータルの導入費用を把握することが重要です。
利益管理ソフトの導入にかかる費用相場
利益管理ソフトの導入にかかる費用は、ソフトの種類、規模、機能、契約形態などによって大きく異なります。
一般的に、クラウド型の小規模事業者向けソフトであれば、初期費用は数万円程度、月額利用料は数千円から数万円程度が相場です。
一方、オンプレミス型のソフトであれば、初期費用は数十万円から数百万円程度、保守費用は年間数十万円から数百万円程度かかる場合があります。
しかし、重要なのは単に価格だけでなく、費用対効果を考慮することです。自社の規模や業務内容に合った機能が搭載されているか、サポート体制は充実しているか、などを総合的に判断し、最適なソフトを選びましょう。
利益管理ソフトの導入費用を抑えるためのポイント
利益管理ソフトを導入する際には、コストを最小限に抑えつつ、必要な機能を確保することが重要です。コスト削減のためには、導入前にしっかりと計画を立て、無駄な支出を防ぐ工夫が求められます。
以下のポイントを押さえることで、より経済的に利益管理ソフトを導入できます。
必要な機能に絞る
利益管理ソフトには多くの機能が搭載されていますが、すべての機能を使うわけではありません。不要な機能が多いと、結果的にコストがかさむだけでなく、操作が複雑になり、業務の効率化が低下する可能性もあります。
そのため、まずは自社の業務フローを整理し、利益管理に必要な機能を明確にすることが重要です。
例えば、基本的な収支管理や利益分析だけ行いたい場合、高度な財務分析や他の業務システムとの連携機能をもつ高価格なソフトを導入する必要はありません。
逆に、複数の事業部門を管理する場合や、データ分析を細かく行いたい場合には、より高度な機能が求められます。導入前に現場の意見を聞きながら、実際に必要な機能をリストアップし、無駄なコストを削減しましょう。
また、導入後に追加機能が必要になる可能性もあるため、後から機能拡張ができるソフトを選ぶのも一つの方法です。拡張性の高いソフトであれば、初期導入コストを抑えつつ、必要に応じて機能を追加することで、柔軟に対応できます。
導入支援サービスを活用する
ソフトの導入時には、初期設定や操作方法の習得が課題となる場合があります。このような負担を軽減し、余計なコストを抑えるためには、導入支援サービスを活用するのが効果的です。
特に、サポートが無償で提供されているソフトを選ぶと、安心して導入・運用ができます。例えば、導入時の初期設定やトレーニングが無料で提供されている場合、専門の技術者を雇用したり外注したりする必要がなく、スムーズに運用を開始できます。
また、運用中に不明点が出た際にも迅速に解決できるため、結果的に業務の停滞を防ぎ、コスト削減につながります。
さらに、クラウド型のソフトであれば、リモートでのサポートを受けることができ、問題が発生した際にすぐに解決できるメリットがあります。無料のサポートサービスを提供しているソフトウェアを選ぶことで、追加費用を発生させずに運用を安定させることができます。また、サポート体制が充実している企業のソフトを選ぶことで、導入後のトラブル対応もスムーズになります。
税制優遇措置を受けられるソフトを選ぶ
利益管理ソフトの導入費用を抑えるためには、税制優遇措置を活用するのも一つの方法です。「中小企業経営強化税制」において、一定の条件を満たしたソフトは設備投資として認められ、税制上の優遇を受けることができます。
例えば、「plusCADシリーズ」のように認定を受けているソフトを選ぶことで、減価償却の特例や税額控除の対象となり、実質的なコストを軽減できます。特に中小企業では、税制優遇の活用により大幅なコスト削減が可能になります。
導入前に、対象となるソフトウェアを確認し、税制優遇を最大限に活用しましょう。専門の税理士に相談するのも有効な手段です。
また、補助金や助成金を活用することでも導入費用を抑えることができます。地域によっては、IT導入補助金などの制度を利用できる場合があるため、事前に情報を調査し、適用可能なものを活用しましょう。
カスタマイズ費用を抑える
業務に合わせたカスタマイズが必要な場合、その費用も考慮する必要があります。一般的に、カスタマイズには高額な追加費用がかかることが多いため、標準機能で対応できるソフトを選ぶことがコスト削減につながります。
カスタマイズの必要性を事前に検討し、業務フローを工夫することで標準機能内での運用が可能か確認しましょう。また、低コストでカスタマイズができるソフトを選ぶのも一つの方法です。開発費用を抑えるために、オープンAPI対応のソフトを活用するのも有効です。
カスタマイズが必要な場合でも、ベンダーによって価格が異なるため、事前に見積りを取ることが重要です。複数の業者と相談し、最適なプランを選択することで、無駄なコストを抑えることができます。
いくつかのソフトを比較検討する
導入費用を抑えるためには、複数のソフトを比較検討し、最適なものを選ぶことが大切です。同じ機能を持つソフトでも、提供元によって価格やサポート内容が異なるため、事前にしっかりとリサーチしましょう。
口コミや導入事例を参考にし、コストパフォーマンスの高いソフトを選ぶことで、長期的に運用しやすい利益管理ソフトを導入できます。
さらに、ベンダーの信頼性も重要なポイントです。長期的に安定して運用できるよう、アフターサポートの充実度や、アップデートの頻度も確認しておくと良いでしょう。
利益管理ソフトの選び方
利益管理ソフトは、企業が収益やコストを効果的に把握し、経営判断を支援する重要なツールです。しかし、選択肢が多いため、自社に最適なものを選ぶことが求められます。
利益管理ソフトを選ぶ際には、いくつかのポイントを重視する必要があります。具体的には、自社の業務に合った機能、使いやすさ、サポート体制の充実度、将来的な拡張性をしっかりと考慮することが重要です。
自社の業務に合った機能を選ぶ
利益管理ソフトを選ぶ際には、自社の業務に適した機能を備えているかどうかを確認することが重要です。業種や事業規模によって必要な機能が異なるため、まずは自社の業務フローを整理し、どの機能が必須なのかを明確にしましょう。
例えば、飲食業であれば売上管理や原価計算機能が求められる一方、製造業では生産コストの管理や在庫管理機能が必要になる場合があります。また、複数拠点を管理する企業では、拠点ごとの収支を一元管理できる機能があると便利です。
さらに、現在使用している他のシステムとの連携が可能かどうかも重要なポイントです。既存の会計ソフトや販売管理システムと連携できるソフトを選ぶことで、データの二重入力を防ぎ、業務の効率化を図ることができます。
使いやすさで選ぶ
次に、使いやすさを重視することも重要です。利益管理ソフトは、データ入力や分析を日常的に行うツールであるため、操作が簡単で直感的に使えることが求められます。
特に、経理担当者やマネージャーが専門的な知識を持っていない場合、複雑な操作は大きな障害になります。使いやすいソフトは、社員の負担を軽減し、業務の効率化を図ることができます。インターフェースのシンプルさや、カスタマイズ可能なテンプレートの有無など、実際に操作してみて使い心地を確認することが大切です。
サポートの充実度で選ぶ
ソフトを導入する際には、サポート体制の充実度も選定基準に含めるべきです。利益管理ソフトを使用する中で、エラーや不明点が発生することがあります。そうした際に、迅速かつ適切なサポートを受けられることは、ビジネスの継続性を確保するために重要です。
サポートがしっかりしているソフトは、電話やメール、チャットサポートなど複数の連絡手段を提供しており、困ったときにすぐに対応してくれます。また、ユーザーコミュニティやFAQが充実している場合も、問題解決の助けになります。
将来的な拡張性を考慮して選ぶ
導入後の運用をスムーズに進めるためには、サポート体制が充実しているソフトを選ぶことが重要です。特に、トラブル発生時に迅速に対応してもらえるかどうかは、業務の安定性に影響を与えます。
サポートが無償で提供されているソフトであれば、追加コストをかけずに問題を解決できるため、長期的な運用コストを抑えることができます。対応時間や問い合わせ方法(電話、チャット、メールなど)も事前に確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、建設業向けの利益管理ソフトについて、導入のメリットから、費用の内訳、相場、コストを抑えるためのポイント、そして選び方まで幅広く解説しました。
利益管理ソフトの導入は、単なるコストではなく、未来への投資です。正確な原価計算、見積り精度の向上、収益性分析、コスト削減、経営判断の迅速化、そしてキャッシュフローの改善など、多くのメリットをもたらします。
賢くソフトを選び、自社の課題を解決し、利益を最大化するための戦略を立てましょう。
建設業15000社の声から生まれた利益管理ソフト「要 〜KANAME〜」
建設業は他の業種と比べて業務フローが特殊なため、一般的な利益管理ソフトだとかえって管理に手間がかかるなんてことは少なくありません。
「要 〜KANAME〜」は建設業15000社の声から生まれた建設業向け利益管理ソフトなので
・事務の方も現場の職人さんも使いやすい!
・工事台帳に情報を集約し一元管理!
・工事ごとの収支をリアルタイムに把握!
・労務費は日報から自動で人工計算!
・作成した見積や注文書を一覧で視える化!
など、迅速な経営判断やコスト削減、見積り精度向上など様々な課題を解決できます。
建設業の利益管理ソフトの導入費用についてよくある質問
利益管理ソフトは、本当に導入する必要がありますか?Excelではダメですか?
Excelは確かに表計算や簡単なデータ管理には便利なツールです。しかし、建設業における複雑な原価計算やプロジェクト管理、収益性分析などをExcelで行う場合、さまざまな課題が顕在化します。例えば、データの入力や集計に膨大な時間がかかり、手作業による人的ミスも発生しやすくなります。また、複数人での同時編集が困難なため、リアルタイムな情報共有がスムーズに行えないという問題も生じます。さらに、セキュリティ面での脆弱性も無視できません。
利益管理ソフトを導入することで、これらの課題を根本的に解決し、より効率的かつ正確なデータに基づいた経営判断が可能になります。自動化されたデータ収集・集計機能、リアルタイムな進捗状況の把握、そして、強固なセキュリティ体制など、Excelでは実現できない多くのメリットを享受できます。事業規模が拡大するにつれて、Excelでの管理は限界を迎えることは明らかです。将来的な事業成長を見据えるのであれば、利益管理ソフトの導入は、必要不可欠な戦略的投資と言えるでしょう。
無料の利益管理ソフトはありますか?ある場合、有料版との違いは何ですか?
はい、無料で利用できる利益管理ソフトも確かに存在します。しかしながら、無料版は、機能制限がある場合や、利用できるユーザー数に制限がある場合、広告が表示される場合など、さまざまな制約が課せられているのが一般的です。例えば、データ保存容量が大幅に制限されていたり、高度な分析機能が利用できなかったり、サポート体制が極めて不十分であったりすることがあります。
有料版は、これらの制限が一切なく、より多くの機能を利用でき、より手厚いサポートを受けることが可能です。また、セキュリティ面でも、有料版の方がより強固な対策が施されていることがほとんどです。無料版は、あくまで試用版と捉え、まずは無料版を実際に試してみて、自社の業務に必要な機能が十分に揃っているか、操作性は快適かなどを慎重に評価し、そのうえで有料版への移行を検討することをお勧めします。
導入費用は一括払いですか?分割払いも可能ですか?また、補助金制度はありますか?
導入費用(初期費用)の支払い方法は、利用するソフトの種類や契約する販売業者によって大きく異なります。一括払いを基本としている業者もあれば、分割払いが可能な業者も存在します。また、リース契約やレンタル契約など、さまざまな支払い方法が用意されている場合もあります。導入を検討する際には、複数の業者に見積りを依頼し、支払い方法について詳細に確認することが重要です。
また、利益管理ソフトの導入には、国や地方自治体が提供する補助金制度を活用できる可能性があります。例えば、IT導入補助金や、中小企業生産性革命推進事業などが挙げられます。これらの補助金制度を活用することで、導入費用を大幅に抑えることができる場合がありますので、導入前に必ず情報を収集し、申請要件などを確認することをお勧めします。
クラウド型とオンプレミス型、どちらが良いですか?それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
利益管理ソフトには、大きく分けてクラウド型とオンプレミス型という2つのタイプが存在します。それぞれに異なるメリットとデメリットがあるため、自社の状況に合わせて慎重に選択する必要があります。
クラウド型:クラウド型の最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点です。また、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、自社でサーバーを管理する必要がないため、メンテナンスの手間も省けます。さらに、ソフトのバージョンアップも自動的に行われるため、常に最新の機能を利用することができます。しかし、月額費用が発生すること、インターネット環境が必須であること、そして、セキュリティ面でオンプレミス型に比べて不安があるというデメリットも存在します。
オンプレミス型:オンプレミス型の最大のメリットは、セキュリティの高さです。自社内でサーバーを管理するため、外部からの不正アクセスを防ぐことができます。また、自社の業務に合わせて自由にカスタマイズできるというメリットもあります。さらに、長期的に見ると、クラウド型よりも費用を抑えられる可能性があります。