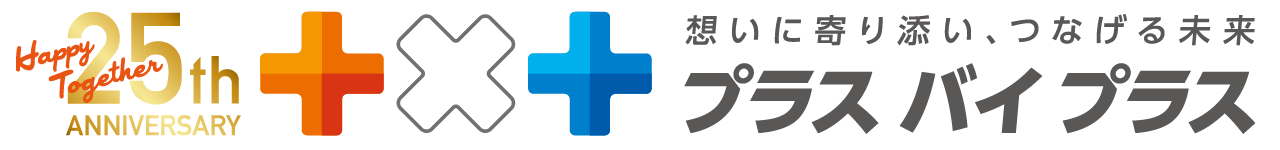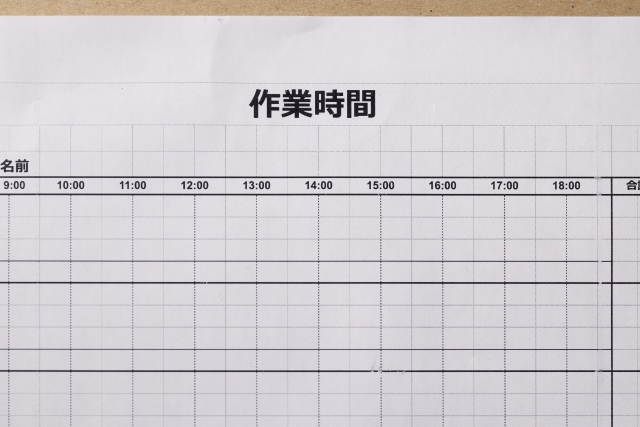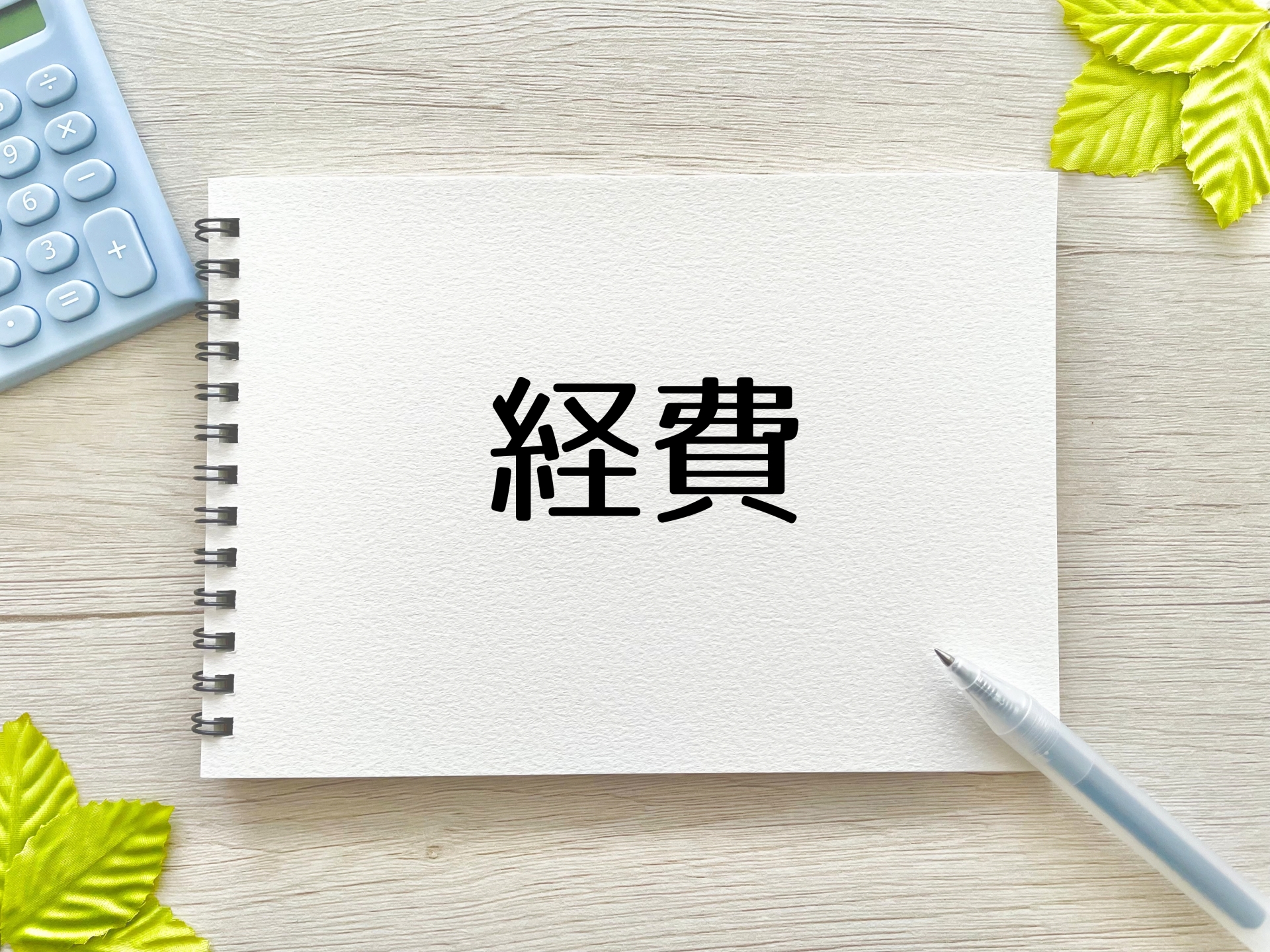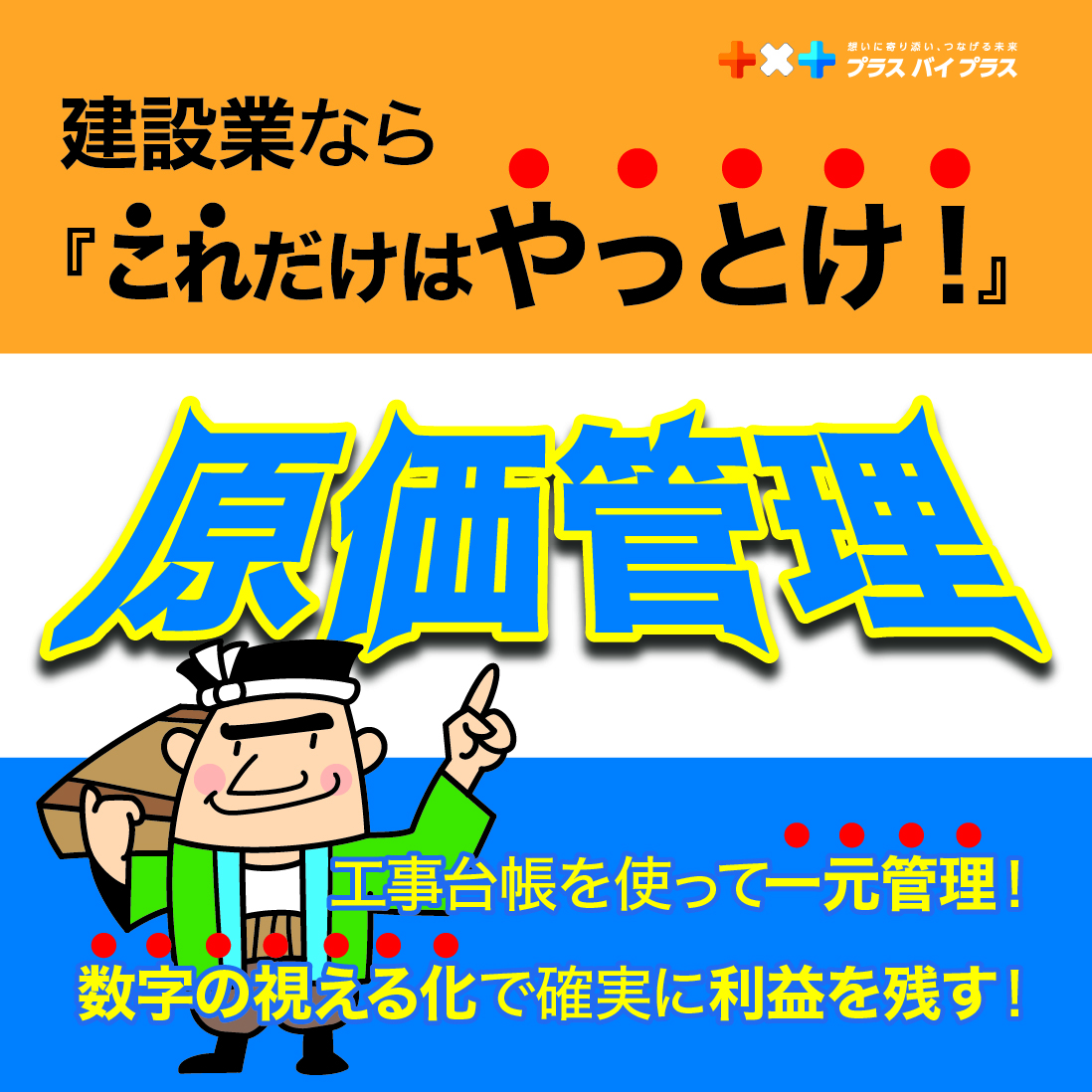- 2025年03月14日
建設業の工事原価管理とは?目的やメリット、建設業の原価管理が難しい理由を解説
案件管理

工事原価管理は、建設業において重要な役割を果たしています。効率的な原価管理を行うことで、プロジェクトの予算を適切に管理し、費用を最適化することが可能です。しかし、建設業は特有の費用構成を持ち、複雑な管理が求められるため、建設業の原価管理は難しいと言われることが多いようです。
この記事では、建設業界の会社が原価管理を行うメリットや難しい理由を解説していきます。
コンテンツ
工事原価管理の基本
工事原価管理は、工事を遂行する上で発生する全ての費用を把握し、適正に管理することを指します。建設業における原価管理では、原材料費や外注費、労務費、経費など、さまざまな要素が絡み合っており、それぞれの費用を的確に把握することが求められます。これにより、企業は予算の管理を効率的に行えるようになり、コストの最適化や事業全体の運営効率向上を図ることが可能です。
また、原価管理は経営戦略を立案するための重要なデータとなり、建設業のような多くのリソースが関わる業種においては、事業運営全般の経営判断にも大きな影響を与えます。正確な原価管理を通じて、企業は利益率の向上や将来的なリスクの軽減を実現することが可能です。
工事原価管理とはどういうものか
工事原価管理とは、工事にかかるすべての費用を詳細に把握し、計画的かつ効率的に運営するための重要なプロセスです。この管理では、発生した費用を分類し、それらの情報を集計することで工事全体の原価を見える化します。具体的には外注費、材料費、労務費をはじめとするさまざまな費用が含まれ、それぞれを正確に計算することが求められます。
また、特に建設業界では、工期の遅れや材料費の変動といったリスクが頻繁に発生するため、適切な原価管理を行うことがプロジェクトの成功に直結します。
建設業における原価管理の重要性
建設業における原価管理は、工事が進行する中で発生する各種の費用を適切に管理するために欠かせない取り組みです。このプロセスを通じて、企業は利益を確保するための基盤を築くことができます。具体的には、正確な原価把握が行われていないと、適切な価格設定や予算の策定が困難となり、結果としてプロジェクトの計画に大きな影響を及ぼします。
一方で、建設業における原価管理を徹底することで、無駄が削減され、効率的なプロジェクト運営が実現可能です。この効率化はプロジェクト単位にとどまらず、企業全体の競争力を向上させる要因ともなります。
したがって、建設業における原価管理を軽視することは、企業にとって深刻なリスクを生む可能性があるため、経営戦略の中で最優先に取り組むべき課題の一つと言えるでしょう。
施工管理と原価管理の違い
施工管理と原価管理は、建設プロジェクトにおいて重要な役割を果たす異なる業務ですが、密接に関連しています。施工管理は、工程や品質、安全管理を含め、プロジェクト全体の進行状況を包括的に把握し、作業を円滑に進める役割を担っています。具体的には、スケジュールの調整や現場の課題解決を行い、納期の遵守とプロジェクトの成功を目指します。一方で原価管理は、プロジェクト費用を効果的に管理するための業務です。資材費や人件費を含むコストの計画、収支の確認、実際の支出との比較を通じて、最適なコストパフォーマンスを実現します。原価管理の正確さは、プロジェクト全体の収益性や予算の適切な配分を確保する上で不可欠です。
施工管理と原価管理は、それぞれ異なる視点からプロジェクトを支えていますが、両者が緊密に連携することで、品質の確保とコスト削減を同時に実現することが可能となります。そのため、施工管理者と原価管理者は、互いの業務内容を理解し、目的に向けて密接に協力することが求められます。
このような協力体制が、建設プロジェクトの成功に大きく寄与します。
工事原価管理の目的
工事原価管理の目的は、工事にかかる総合的な費用を適切に把握し、計画的に運営することにあります。適切な予算管理を行うことで、利益の確保やコストの最適化という経営の重要な要素を実現し、原価を正確に管理することが可能となります。これにより、経営資源を有効に活用し、無駄な支出を削減することで、効率的かつ持続可能な経営体制を構築できるのです。
予算管理の基盤構築
予算管理は、建設業において非常に重要な要素です。工事原価管理によって作成された予算は、プロジェクトが開始される前の基盤となります。この段階で、正確な原価の見積もりを行い、原価管理表を活用することで、プロジェクト全体の方向性を定めることが可能です。
適切な予算管理は、進行中のコストを可視化し、必要に応じた修正を早期に行うための指針となります。また、こうした管理を通じて、関係者や顧客との信頼関係をより強固に築く土台を形成します。
実績と予算の差異管理
実績と予算の差異管理は、工事原価管理において欠かせない重要な業務の一つです。実際に発生した費用と実行予算を比較することで、予算管理の観点からどの部分で予算を上回っているか、または下回っているかを正確に把握できます。この分析により、必要に応じて計画の修正や効果的なコスト削減施策の実施が可能となります。また、こうしたプロセスを実行することで、プロジェクトの進捗状況をより明確に把握でき、全体の予算管理が強化されるとともに、経営判断を迅速かつ適切に行う基盤が整います。建設工事における費用管理の最適化
建設工事における費用管理の最適化は、経営の効率を向上させるために欠かせない作業です。建設業における原価管理を徹底することで、原価を正確に把握し、不要なコストを削減してリソースを効率的に活用できます。このような管理体制を整えることは、工事の最適な進行を支える要素であり、プロジェクト全体の成功にも直結します。
また、各工程のコストを継続的にモニタリングし、適宜調整を行うことでコストの無駄を抑えられ、結果として経営状態を健全に保つことが可能です。
こうした継続的な費用管理の取り組みは、短期的な目標達成に留まらず、建設工事を効率的かつ持続的に運営するための基盤を構築します。
工事原価管理がもたらすメリット
工事原価管理を導入することにより、様々なメリットが企業に提供されます。まず、工事に関する原価管理を行うことで、工事目的に必要な費用を詳細に測定・分析することが可能になり、実際のコストを正確に理解しやすくなります。このプロセスによって、コスト管理が徹底され、予算に対する具体的な支出額を正確に把握できるようになります。このような透明性は、経営者や管理者が迅速かつ的確な意思決定を行うための重要な支援となります。
また、工事の目的達成に必要なリソース配分を最適化し、無駄な支出を抑えることで、全体的な業務効率を向上させる一助となります。
工事コストの可視化
工事におけるコストを可視化することは、原価管理の重要な要素です。原価管理表を活用して費用の詳細を一覧化することで、各プロジェクトにおける資源の使い方を一目で確認できます。これにより、特定の工程や使用する資材がどの程度コストを押し上げているのかを正確に把握することが可能です。具体的なデータに基づき判断を行うことで、経営陣は無駄を削減し、より効率的な戦略を策定できます。工事の進行状況やコスト面の課題を詳細に把握することにより、全体的な生産性向上にも寄与します。
プロジェクト収益性の向上
工事原価管理は、各プロジェクトの収益性向上を目的とした重要な手法です。費用が明確に把握できることで、利益率を高めるための具体的な対策を立てやすくなり、必要に応じて迅速に改善策を実行することが可能となります。このアプローチにより、収益を最大化するための効率的なプロジェクト運営が実現します。
特に、競争が激化しているゼネコンをはじめとする建設業界において、利益の向上は企業の生き残りに直結するため、この取り組みのメリットは極めて大きいです。
無駄なコスト削減による利益確保
無駄なコストの削減においても、ゼネコンを含めた工事原価管理は大きな効果を発揮します。この管理手法を適切に活用することで、支出に関する情報を正確に把握し、不要な経費を具体的に特定することが可能になります。そして、その情報を基にした効率的なやり方で削減策を講じることで、経費の最適化が図れるだけでなく、経営全体の効率性が向上します。このような取り組みは、最終的には利益確保に直結します。
また、コスト削減を進める中で採られる適切なやり方は、組織全体の経営姿勢を見直し、改善につなげるという重要な役割も果たします。これにより、持続可能な成長を目指す企業経営が可能となります。
工事原価管理が難しい理由
工事原価管理は、その複雑さから多くの企業にとって大きな課題です。建設業の原価管理では、設計段階から施工完了までの全プロセスにおいて、多岐にわたる要因が影響を及ぼします。その結果、正確な原価の把握が難しくなる場合があります。また、工事の進行状況によって原価が変動することが多々あり、これも管理をさらに困難にする要因です。しかし、経営者や管理者がこれらの課題を効果的に克服することで、業務全体の効率化や利益率の向上が期待できます。
複雑な費用構成の管理
建設工事は、多様な費用要素が絡み合っているため、その構成を管理することが難しいです。直接工事費、外注費、間接費など、さまざまな種類のコストが発生します。これらの費用を正確に把握し、適切に配分するためには、専門的な知識と時間が必要です。また、工事の規模や内容によっても費用構成が異なるため、現場ごとの特性に応じた管理が求められます。特に効率的な管理のためには「原価管理表」を活用することが効果的です。「原価管理表」は、各費用要素を一元的に整理し、明確な記録を残すことで、全体の状況を把握しやすくなるツールです。適切なやり方でこれを運用することで、コスト管理の効率化が期待できます。また、費用管理の改善点を迅速に発見できるため、現場ごとの費用の偏りやムダの削減にも繋がります。
原価科目の特殊性
建設業には特有の原価科目が存在し、これが原価管理をさらに難しくさせています。一般的なビジネスの会計とは異なり、建設業には「完成工事原価」や「未成工事支出金」といった特殊な科目が必要です。これらの科目とは、プロジェクトごとの収益や費用を正確に把握するために欠かせないものです。そのため、これらの項目を適切に分類し、記録することは会計担当者にとって大きな負担となります。また、間接的な費用についても細かく分類する必要があり、このプロセスを効率化するためには、原価管理表の活用が極めて重要です。原価管理表を用いることで、管理フローの複雑化を軽減しつつ、正確なデータ管理と分析が可能になります。
外注費の計上と管理の難しさ
工事に関連する外注費の管理は、非常に難しいタスクです。外注業者への支払いや契約内容を正確に追跡することが要求されますが、その手続きが煩雑であるためです。また、外注先ごとに異なる料金体系や契約条件があることにより、費用を正確に計上するためには高度な注意が必要です。このため、外注費が工事全体のコストにどれほど影響を及ぼしているのかを把握することは簡単ではありません。そのため、多くの企業では「原価管理表」の活用が重要となっています。原価管理表を作成・運用することで、外注費を含む工事全体のコストを詳細に把握し、計画的に管理することが可能です。特に外注費の記録と分析を一元化することで、予算超過を防ぎ、効率的な運営を実現する手助けとなります。
こうした最適な管理方法を採用することで、外注費管理に伴う労力を軽減するだけでなく、全体のコスト管理を改善することが期待できます。
収益認識基準の対応
工事原価管理における収益認識基準の適用は、企業にとって大きな課題となっています。特に、契約に基づく収益の計上方法は新しい基準に従う必要があり、ゼネコン業界を含む多くの企業において対応が求められています。このような新基準を適切に反映させるためには、既存の会計体制を根本から見直し、効率的なやり方を模索する必要があります。また、これに伴い社員への教育プログラムの導入や業務に対応するシステムのアップデートも必須となり、これらの対応が経営資源の消耗を引き起こしかねません。企業がこうした課題を乗り越えるには、綿密な計画と効率的な運用が求められるでしょう。
実行予算と原価管理の関係
実行予算と原価管理は、建設業における経営の根幹を成す重要な要素です。実行予算は工事にかかる総コストを正確に把握し、それを基に計画的な運営を行うための基盤を提供します。これにより、工事が計画通りに進行するだけでなく、実績ベースでの評価を可能にし、効率的なコストコントロールが実現します。また、予算管理を適切に行うことで、予算超過や無駄なコスト増加を未然に防ぐ効果が期待できます。これらを統合的に運用することで、企業全体の効率性と利益率の向上につながります。
実行予算の役割
実行予算は、プロジェクト管理において不可欠な要素であり、その主な目的は計画の実行を効果的に支援することにあります。特に建設工事の分野では、実行予算を設定することで、必要な資源や作業量を正確に把握でき、工事全体の進捗状況を適切にモニタリングすることが可能となります。このような明確化を通じて、計画通りのコスト管理が実現しやすくなります。また、関係者全体がこの予算を共有することで、目的を共通認識として持つことができ、全体の連携を強化し、プロジェクトの円滑な推進につながります。
予算管理と原価管理の統合
予算管理と原価管理の統合は、実行予算を効果的に活用し、プロジェクトの成功を支える重要なプロセスです。予算を元にした原価計算を通じて、実際にかかったコストが予算とどの程度乖離しているかを定量的に把握することができます。この際、原価管理表を活用することで、コストの詳細な内訳や分析が容易になり、プロジェクト全体の透明性が向上します。さらに、このプロセスの中で得られた情報を基にプロジェクト進捗を分析し、必要な改善策を速やかに講じることが、成果を上げるためには不可欠です。
また、常にリアルタイムでデータが更新される環境を整備することで、予算管理の精度が高まり、タイムリーかつ的確な意思決定が可能となります。これにより、予算と実コストの差異を即座に把握し、問題が発生した場合には迅速な対応が取れるようになります。
このように、予算管理と原価管理表を組み合わせた統合的な管理体制は、建設をはじめとする多様なプロジェクトにおいて、効率的かつ成功率の高いプロジェクト運営を実現する重要な要素です。
建設業向け工事原価管理システムの選び方
工事原価管理システムの選定は、建設業における効率的な運営や利益向上において欠かせない重要なステップです。適切なシステムを導入することで、建設業における原価管理の精度を高め、業務フロー全体の効率化を図ることができます。また、各社の多様なニーズに対応したシステムを選ぶことが利益の最大化につながります。そのためには導入に際し、機能面や業務適合性をはじめとした様々なポイントを丁寧に検討し、慎重に選択することが何よりも重要です。
システム導入の目的を明確にする
システムを選定する際には、まず導入の目的を明確に設定することが重要です。目的を具体的にすることで、企業が解決したい課題や達成したい成果が明確になり、適切な解決策を見つけやすくなります。例えば、原価管理の効率化や業務プロセスの最適化を目的とするならば、それに対応可能な機能を持つシステムを選ぶ必要があります。また、目的に基づいてシステムの機能要件を定義することで、業務に最適な製品の選定がスムーズになります。目的が明確であれば、市場に数多く存在する選択肢の中から、貴社のニーズに合ったシステムを効率的に見つけ出すことが可能になります。
クラウド型かオンプレミス型か
システムの選定において、クラウド型かオンプレミス型かを選ぶことは重要なポイントの一つです。それぞれにメリットとデメリットが存在し、企業のニーズに応じた適切な選択が求められます。クラウド型とオンプレミス型の比較例(※あくまで一例のため製品によって違いがあります)
| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 低い | 高い |
| ランニングコスト | 月額・年額課金(スモールスタートしやすい) | 一度の投資で長期的にコストを抑えられる |
| 導入スピード | 早い(すぐに利用開始可能) | 計画的な導入が必要 |
| セキュリティ | ベンダーに依存(最新対策が施されている) | 情報漏洩の可能性が低い |
| 利用場所 | インターネット環境があればどこでも利用可能 | 社内環境での運用が中心(オフラインでも安定して利用可能) |
| インターネット依存 | 必要(ネット接続がないと利用不可) | 不要(社内ネットワークのみで安定稼働) |
クラウド型とオンプレミス型それぞれの特徴を十分に理解し、自社の業務形態や今後の拡張性を考慮して選択することが重要です。
一元管理機能と工事対応能力の確認
選定候補のシステムには、一元管理機能が搭載されているかを確認することが非常に重要です。この一元管理機能を活用することで、複数のデータを効率的にまとめて管理でき、業務全体の効率化が期待できます。特に、システムが工事対応能力を備えているかも重要な要素となります。具体的には、工事の進捗状況、発注内容、経費管理を同時に把握できる機能があれば、必要に応じた迅速な意思決定が可能となり、業務の精度と効率が向上します。これらの機能の充実度を比較検討し、システムが自社の工事管理業務をどれほど効果的にサポートできるかを慎重に見極めることが、最適な選定に繋がります。
まとめ
建設業における工事原価管理は、企業の経営において極めて重要な要素です。適切な原価管理を実施することで、コストを可視化し、プロジェクトの収益性向上を図ることができるだけでなく、無駄な支出を削減することで効率的な運営が可能となります。このような取り組みを通じて、企業は競争力を強化し、持続的な成長を実現する基盤を確立することができます。さらに、建設業の原価管理においては、実行予算との関係を深く理解することが重要です。予算管理と原価管理を適切に統合することで、リアルタイムでコストの動向を把握できるようになり、その結果、迅速かつ適切な意思決定が可能となります。特に、工事に必要なリソースの配分や管理が簡素化され、プロジェクト全体の効率向上にもつながります。
また、工事原価管理においては、適切な管理システムの選定がプロセスの効率化と精度向上に直結します。システム導入時には目的を明確にし、クラウド型とオンプレミス型の特性を比較検討することが求められます。これにより、自社の課題や規模にマッチした最適なソリューションを導入できるでしょう。建設業の原価管理を成功させるにはこれらのポイントを押さえることが欠かせません。結果として、効率的で透明性の高い工事運営が可能となり、建設業全体の健全な発展が期待されます。
建設業の原価管理は専門の原価管理システムがおすすめ
冒頭でもお伝えした通り、建設業界は特有の費用構成をしているため、一般的な原価管理システムでは業務フローや管理項目が合わず、管理にかかる労力が増えるにもかかわらず、結果的に管理もまともにできていない・・・なんてことになりかねません。可能な限り手間なく、シンプルな管理を行うためには建設業専門の原価管理システムの導入がおすすめです。
建設業向けの原価管理システム「要 〜KANAME〜」は、工事台帳に全てのデータを紐づけることでシンプルに社内へ情報共有できます。
・工事ごとの収支をリアルタイムに把握!
・労務費は日報から自動で人工計算!
・作成した見積や注文書を一覧で視える化
「要 〜KANAME〜」紹介動画を見る
<「要 〜KANAME〜」の詳細を見る>