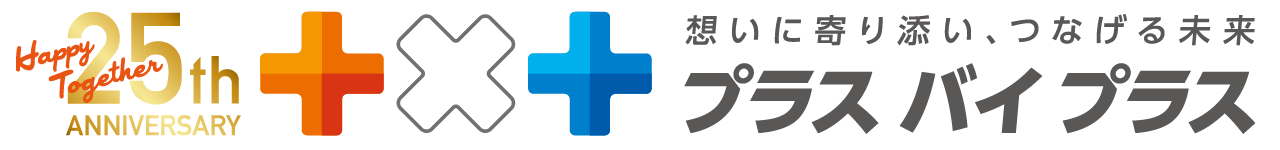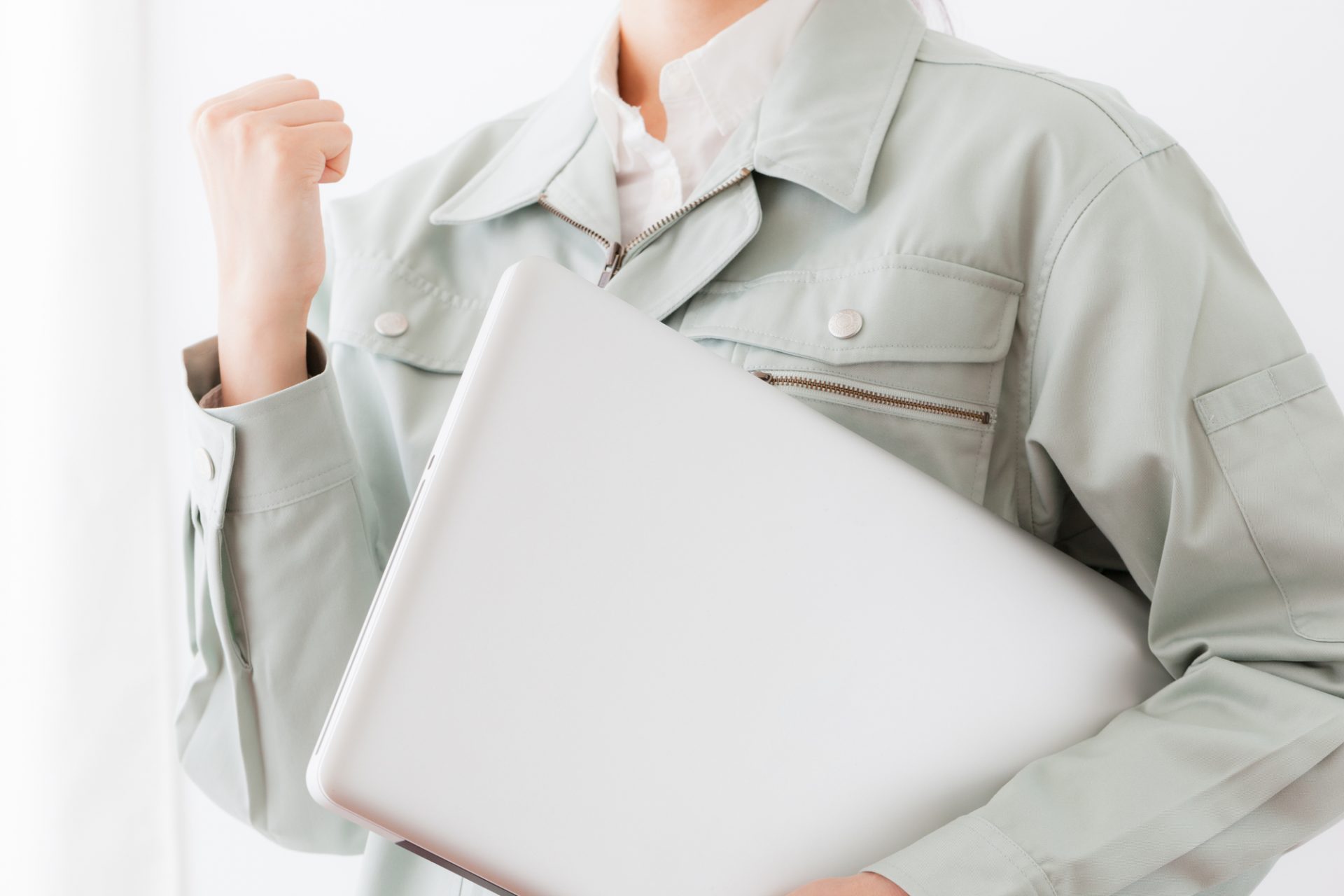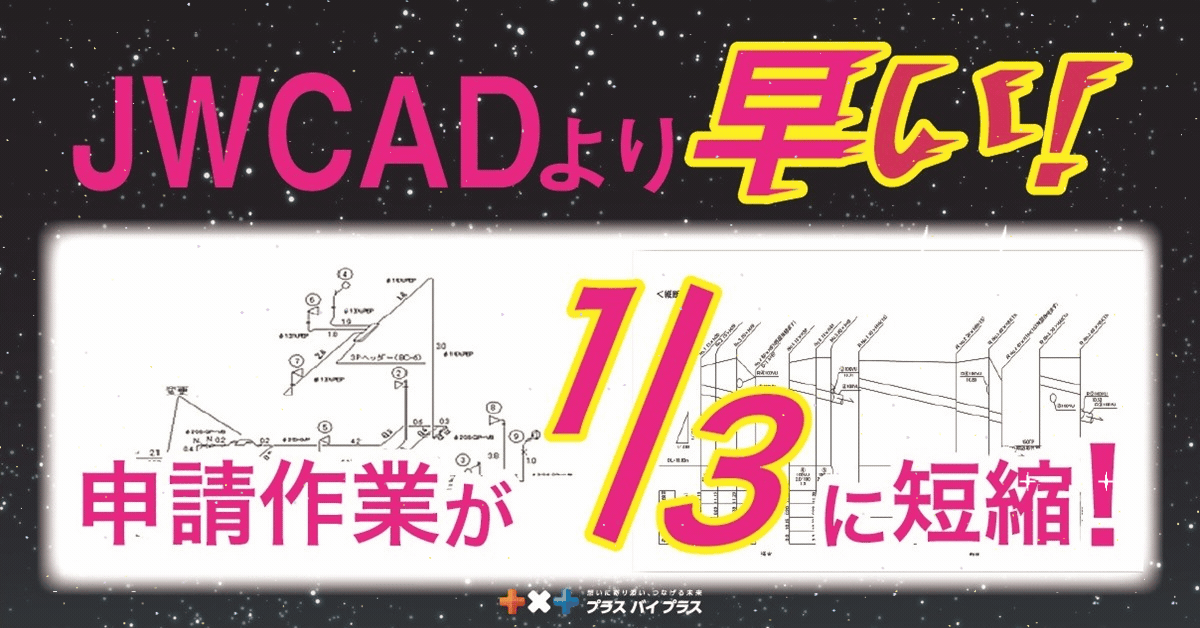- 2025年02月07日
配水管と給水管の違いとは?配水管を設計する流れや素材選定で満たすべき要件を解説

水やガス、空気を運ぶ配管は、さまざまな場面で重要な役割を担います。「給水管」は水を供給する管であり、「配水管」はその水を各所に分配する管です。配水管に不備があると、水が行き渡らない、排水が滞るといったトラブルが発生します。本記事では、配水管の設計手順や素材選びについて解説します。適切な設計・施工を理解し、業務に役立ててください。
コンテンツ
水道管とは?
水道管とは、水道システムにおいて水を供給するための管のことを指します。主に給水管と配水管に分類され、給水管は水源から家庭や施設へ水を送る役割を果たしています。一方、配水管は各種の水道メータから水を供給し、さらに一般の利用者に分配する重要な役割を担います。
水道管は、材料や設計によって耐久性や安全性が異なり、適切な選定が求められます。また、地中に埋設されることが多いため、周囲の環境や埋設深度に影響されることもあります。このような特性から、適切な維持管理が必要となり、地域住民の生活を支える基盤として重要な存在です。水道管の選定や設計においては、これらの要素を考慮することが不可欠です。
配水管と給水管の違いとは?
配水管と給水管は、水道システムにおいて重要な役割を果たしますが、その機能と位置づけには明確な違いがあります。給水管は、井戸や水源から取水した水を家庭や商業施設、工業用地などへ供給するための管です。このため、給水管は一般的に水圧を確保し、流量を適切に維持する設計が求められます。一方、配水管は、すでに供給された水を各所に分配する役割を担っています。配水管は、給水管から供給された水を受け取り、住宅や施設のニーズに応じて配分します。
配水管の設計では、多くの要素が考慮されます。例えば、配水管が所定の地域に配置された場合、家庭用の需要を見込んで管径や材質を選定する必要があります。この際、周辺環境や将来の建設計画なども考慮され、柔軟な設計が求められます。また、配水管は排水に関しても影響を与えるため、排水管との併設計画を立てることも重要です。これにより、水の流れがスムーズになり、トラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、配水管と給水管の材質選びも重要なポイントです。給水管に使用される素材は、耐食性や耐圧性が求められるためポリエチレンや亜鉛メッキ鋼管が多用されます。一方、配水管は土壌環境や埋設深さに応じた適切な素材選定が必要で、特に埋設場所の水分量や土の性質により耐久性が求められます。このように、配水管と給水管は、技術的な観点から見ても異なる要件を満たす必要があります。
また、送水管の概念も理解しておく必要があります。送水管は、給水施設や水源から配水管までの間に設置されるもので、主に大量の水を長距離で移動させるために設計されています。このため、送水管は高い圧力に耐えられるような強度が求められるほか、材質選定にも細心の注意が必要です。例えば、送水管には耐腐食性のあるステンレス鋼やポリ塩化ビニル(PVC)が使用されることが多いです。これにより、効率的に水を各地域に送ることが可能になります。
このような理解をもって両者の違いを把握し、適切な設計と施工を行うことは、実際のインフラ整備において非常に重要です。正しい配水管と給水管、そして送水管の選定により、地域全体の水道システムの信頼性や持続可能性が確保されます。
配水管設計の手順
ここからは、配水管設計の流れについて解説します。配水管設計における主な手順は、以下の通りです。
・現地踏査
・道路工事調整
・測量・調査
・埋設物調査
・管理者との協議
・用地の確認
・地域住民への説明
・設計
各項目について詳しく見ていきましょう。
現地踏査
まずは、設計対象となる場所の現地踏査を行い、環境や状況を確認します。現地踏査とは、土地の地形や地質、沿道の利用状況、支障物件の有無、埋設物などを調べることです。主に、以下のような項目を確認します。
・道路状態:道路種別や幅員、道路屈曲状況、交通量、交通規制の状況、迂回路、スクールゾーン、バス運行時間など
・地上・地下構造物:管路の付帯施設や電柱、架空線、標識、ガードレール、橋梁の位置など
・路線周辺の状況:騒音や振動など沿道構造物への影響など
・関連事業:他社との競合工事の有無や施工時期など
道路工事調整
続いて、配水管工事に関係する道路工事調整の手続きについて確認しましょう。公道を掘削しなければならない場合、道路交通法(第77条)に基づき、所轄警察署に申請して道路使用許可を取得する必要があります。
道路を頻繁に掘削すると、道路交通の障害となるうえ、資源の無駄にも繋がるため、一度路面を復旧した後は、一定年次掘削を伴う工事ができなくなる掘削抑制措置が取られています。そのため、長期的な計画を踏まえて、工事区間や時期を調整しなければならない場合もあります。
道路管理者、交通管理者、各占用企業者から構成される道路工事調整協議会が設けられている場合は、それぞれで決められた様式に道路名や施工場所、工法などの必要事項を記載し、提出します。また、合理的かつ円滑的に工事が進むように、他業者工事との同時施行の有無や近接工事との兼ね合いなどで施工時期の調整が必要な場合もあります。
測量・調査
工事の規模や施工環境に応じて、測量調査や地質調査を実施します。配水管工事の測量調査では、以下のような測量を実施します。
・水準測量:既知点に基づいて水準点の標高を定める
・現地測量:実施設計に必要な平面詳細図を作成するために現況の地形や地物を測定する
・路線測量:中心線測量、銃弾測量、横断測量
地質調査では、工事場所付近の既存の土質調査結果を参考とします。詳細な構造計算が必要な場合は、標準貫入試験や土質試験などの地質調査も行います。
埋設物調査
配水管工事では、埋設物の調査も重要です。基本的には、埋設物の管理者の図面や現地踏査を使用して、工業用水道や下水道、電気、ガスなどの配管の占用位置、形状、寸法などを明確に把握します。その後、必要に応じて地下埋設物調査などを実施して、埋設状況を確認します。
埋設物が古く、実際の埋設状況が図面や管理台帳の内容と大きく異なる可能性があるときには、試掘調査を実施する場合もあります。試掘調査では、地下埋設物の種類や位置、深さ、構造を調べ、管理者が所有する資料の情報と照合します。
管理者との協議
配水管設計に向けて、該当する管理者と協議を行う必要があります。例えば、道路専用工事が必要な場合は道路管理者と、また河川を占用する場合は河川管理者と協議を行います。
他にも、所轄消防署や軌道管理者、公共交通機関担当部署、公園管理者などとの協議や調製を実施するケースもあります。工事が必要となる場所の状況や環境によって、ケースバイケースで協議や調整が入るため、協議期間や資料などもそれぞれで変わります。
用地の確認
配水管は原則として道路などの公共用地に埋設しますが、やむを得ず私有地に埋設しなければならない場合は、用地の買収もしくは地上権の設定などの対応が理想的です。そのため、事前に用地調査などを通して確認しておく必要があります。
用地調査では、公私の不明確な場所について公図や土地台帳などを使って調査、確認を行います。借地の場合は、土地所有者の承諾を事前に文書で得ておくと無難です。
地域住民への説明
大規模な工事など、工事により影響が出る地域や関係するエリアの住民に対して、事前説明を行い、理解を得ておくことも重要です。
工事期間中に通行止めを行う時期や騒音、振動などの可能性がある場合、地元説明会を開催するなど近隣住民に周知しておきましょう。
設計
配水管の設計では、多くの図面を作成する必要があります。基本的には、設計図、特記仕様書、施工計画書、数量計算書、工事費積算書などが必要です。
配水管の管種や口径、工事の始点・終点などの設計条件を明確にしておきます。占用位置に関しては、現地踏査や埋設物調査を基に、道路管理者との協議によって決定しておくとスムーズです。
配水管の素材選定で満たすべき要件
配水管の素材を選ぶ際には、安全性や埋設条件、埋設環境への適合などさまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。また、水道法において定められた水圧の範囲内に収めることも重要です。ここでは、配水管の素材選定における要件について解説します。
安全性
配水管に用いられる素材の種類は、後の章で詳しく解説しますが、ダクタイル鋳鉄やステンレス、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、ポリエチレンなど多数あります。
配水管の素材を選ぶ際には、材質による浄水の汚染のおそれがなく、水道法の規定に基づく「技術的基準を定める省令」に示された浸出基準を満たしているもので、且つ安全性が確認されている必要があります。
水圧を考慮した強度
配水管では、水圧を考慮し、破損に耐えうる強度であることも重要です。水道法に基づく技術的基準を定める省令により、配水管の水圧は「配水管から給水管に分岐する箇所での配水管内の水圧は、150kPa(0.15MPa)以上740kPa(0.74MPa)未満を維持する」よう定められています。
配水管の用途として、中を通る水の外力や内圧に耐える強度も必要です。外力は、破裂の可能性のある土圧や路面荷重、地震力なども考慮して決める必要があります。
また、内圧では、実際に使用する管路の最大静水圧と、水撃圧を踏まえて決定します。素材により目安の水撃圧は異なり、ダクタイル鋳鉄管や鋼管、ステンレス鋼管では0.45MPa〜0.55MPa、硬質ポリ塩化ビニル管やポリエチレン管では0.25MPaとされています。
埋設条件や埋設環境への適合
素材選びでは、土質や地下水の状況や路面荷重など埋設場所の諸条件を考慮して選ぶことが大切です。腐食性の強い土質や地下水がある場所では、防食性のある素材が適切です。また、ガソリンや灯油など有機溶剤の影響が想定される場合は、ポリエチレン管や硬質ポリ塩化ビニル管は避けるべきでしょう。
その他の地下埋設物がある場所や、埋戻しが行われるような場合は、継ぎ手構造に対する施工性も考える必要があります。埋設環境によっては、柔軟性のある伸縮継ぎ手の仕様を検討すると良いでしょう。
配水管に使う素材の種類とその特徴
配水管の種類には、ダクタイル鋳鉄管、鋼管、ステンレス鋼管、硬質ポリ塩化ビニル管、水道配水用ポリエチレン管などがあります。それぞれの素材によって強度や製造方法、維持管理のしやすさなどの条件が異なるため、施工場所に最適なものを選ぶことが大切です。
現在、水道管に使用されている主な管種の種類と特徴を大まかに説明します。
【ダクタイル鋳鉄管】
ダクタイル鋳鉄とは、従来の鋳鉄の組織中に、細長い片状に分布していた黒鉛を球状化させた鋳鉄のことです。ダクタイル鋳鉄管では、強度や延性が改良されています。重量は比較的重めですが、衝撃に強く施工しやすいため、継ぎ手部品にも使われています。
【HIVP管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)】
HIVP管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)は、近年主流となっている樹脂製の水道管です。プラスチック製のため、錆び付きが起きる心配がありません。軽量で加工しやすく、施工時や修理コストが安く済む点もメリットです。ただ、急激な温度の変化に弱く、水道が凍結すると割れる可能性があるため、寒冷地には不向きでしょう。
【ポリエチレン管】
HIVP管のデメリットを補う形で使われているのが「ポリエチレン管」です。管と継ぎ手を接着剤やテープなどを使わずに接続でき、取り付けが容易で扱いやすいため、さまざまな場所で使われています。また、振動や熱、化学物質による影響を受けにくく、耐震性も確保できます。ただ、価格がやや高く、紫外線に弱いため、場所や用途によってHIVP管とポリエチレン管を使い分けるケースが増えています。
【ステンレス管】
錆びにくいステンレスを使用したステンレス管は、高価ではあるものの100%リサイクル可能で長く使えるため、現在需要が高まっています。塗装なしで使えるため、地上露出部などでも採用されています。
まとめ
配水管は、浄水場から消費者まで水を届ける重要なインフラであり、その設計や素材選定は長期間にわたる劣化や水漏れを防ぐために不可欠です。まず、耐用年数を考慮することが重要です。一般的に、ポリ塩化ビニル(PVC)製の配水管は約50年の耐用年数が期待されていますが、環境条件や使用状況によっては、メンテナンスが必要となることがあります。
さらに、配水管は地下に設置されるため、埋設環境の影響を受けやすくなります。例えば、土壌の化学的性質や地下水位が高い地域では、管の劣化が早まる可能性があります。そのため、定期的な点検を通じて水漏れを早期に発見し、必要に応じてメンテナンスや取り換えを行う体制が重要です。実際に、水漏れが発生した場合、一日あたりの漏水量が数立方メートルに達することもあり、これが長期間続くと莫大な水道料金の増加や周辺環境への影響を及ぼす恐れがあります。
メンテナンス方法としては、光ファイバーを用いた漏水検知システムや、非破壊検査技術を活用することが進められています。これにより、事前に配水管の状態を把握し、早期に対処することが可能です。加えて、取り換えの際には、従来の素材に加えて、新しい技術を活用した耐久性の高い素材を選定することで、将来的なリスクを軽減できます。
このように、配水管の設計・素材選定においては、耐用年数やメンテナンスの重要性を認識し、環境に適した素材選びが求められます。劣化の進行を抑えることで、配水管の供給能力を維持し、安全で安定した水供給を実現することが可能になります。
「plusCAD水道Ⅴ」で図面を業務効率化、正確な図面作成を実現
配水管設計には測量・基盤調査・基盤図作成など複雑な手順が必要です。「plusCAD水道Ⅴ」は、給排水工事の申請書作業を大幅に短縮できるCADソフトです。 パソコンが苦手な方でも、エクセルやワードのような直感的な操作が可能で、マウスの左クリックだけで図面が描けます。 さらに、平面図を描けば立面図・縦断図を自動で作図ができます。
「plusCAD水道Ⅴ」の利点
・簡単操作:マウスの左クリックだけで図面作成が可能。
・自動作図:平面図を作成するだけで、立面図・縦断図を自動生成。
・直感的操作画面:エクセルやワードのような感覚で操作可能。
・作業時間短縮:申請書作成を大幅に効率化。
これらの機能により、作業効率が飛躍的に向上し、業務の生産性を高めることができます。
詳細は「plusCAD水道Ⅴ」の紹介ページをご覧ください!