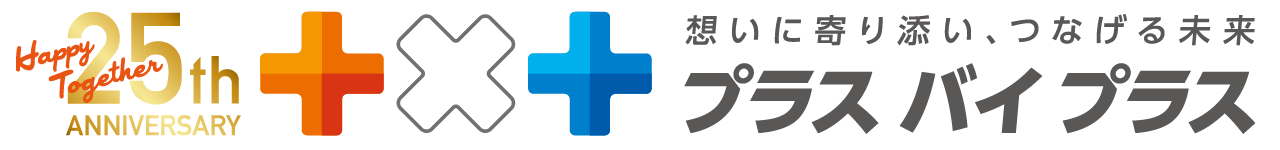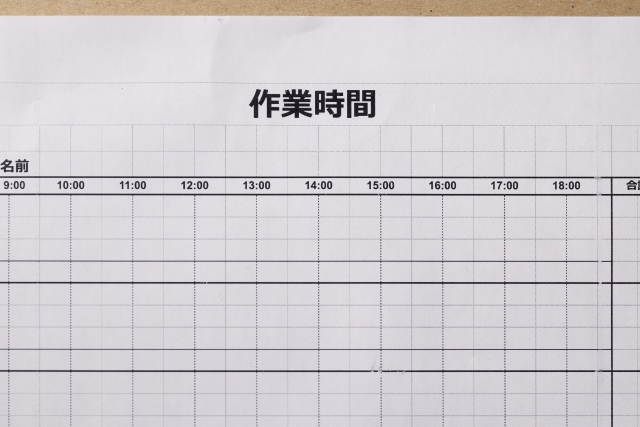- 2025年04月01日
【建設業の経営改善】経営課題とすぐ実践できる10の施策

建設業界は、経営改善を進めるうえでさまざまな課題を抱えています。市場の競争激化や人手不足、技術革新への対応の遅れ、原材料費の高騰といった課題に直面し、日々の経営が厳しくなるなかで、どのように経営を改善していくべきかが問われています。この記事では、建設業における経営改善に必要な施策を紹介し、すぐに実践できる改善策を解説していきます。
コンテンツ
建設業における経営課題
経営改善の第一歩は、業界の現状をしっかりと把握することです。建設業界に特有の課題を理解し、それらに対処する方法を考えることが重要です。
人手不足と高齢化
建設業界は他の業界に比べて人手不足と高齢化が顕著です。多くの現場作業員が高齢化しており、若年層の労働力の流入が少ないため、労働力の確保が急務です。
加えて、労働環境の厳しさから他業種に流出する若者も多く、結果的に技術者や作業員が不足し、現場の効率が低下する要因となっています。建設業の経営改善の一環として、労働力の確保や若年層の雇用促進が鍵となります。
労働時間と働き方改革
建設業では、長時間労働が常態化していることが多く、従業員の健康やワークライフバランスに対する配慮が不足しているケースもあります。
働き方改革が求められるなかで、業務の効率化や休暇制度の見直し、柔軟な勤務形態を導入することが、経営改善を進めるためには欠かせません。たとえば、作業のスケジュールを効率的に組み替えることで、労働時間の短縮を図ることができます。
競争激化と価格競争
市場競争が激化するなかで、価格競争も利益を圧迫する要因となっています。安価な工事提案が求められる場面もあり、利益率の低下を招いています。
そのため、コスト削減だけでなく、品質や技術面での優位性をアピールすることが、競争を勝ち抜くためのカギとなります。価格競争を避けるためには、他社との差別化を図ることが重要です。
原材料費の高騰
最近では、原材料費の高騰が経営改善の大きな障壁となっています。鉄鋼や木材、セメントなどの資材費が上昇し、これが施工費の高騰を引き起こしています。経営者は、原材料費の動向を予測し、コスト管理を徹底することが求められます。また、長期的な調達契約を結ぶことや、資材の新たな購入ルートを探すことも有効な手段です。
下請け体質
多くの建設業者が下請けに依存しており、これが利益率の低下を招いています。
この状況を改善するためには、直接契約の割合を増やし、利益率の高い案件を確保することが必要です。
資金繰りの悪化
建設業では、工事が完了するまでの間に支出がかさむことが多く、資金繰りが悪化しやすいという特徴があります。
特に、大型工事の場合、着工から完工まで長期間を要するため、その間の資金調達が必要不可欠です。短期的な資金調達手段を確保し、キャッシュフローを常に把握しておく必要があります。
技術革新への対応の遅れ
建設業界では、IT技術や機械化の導入が遅れがちです。これらの技術革新を適切に導入することで、生産性を向上させ、コスト削減や業務効率化が実現できます。
ドローンや3Dプリンティング技術を活用した現場管理や、図面作成と見積もりの連動による業務効率化など、新しい技術を積極的に導入することで、競争力を高めることができます。
経営改善のための具体的な10の施策
建設業界は競争が激しく、また外的な要因にも大きく左右されるため、経営改善を進めるためには戦略的な取り組みが大切です。
ここでは、建設業における経営改善のためにすぐ実践できる10の施策について詳しく解説します。これらの施策を導入することで、業績向上や持続的な成長を実現できるでしょう。
業務効率化
業務効率化は経営改善において最も基本的で効果を得やすい施策の一つです。業務を効率よく進めることで、コスト削減と時間短縮が実現し、リソースの有効活用が可能になります。
例えば、施工管理や工程管理、見積もり作成をデジタル化することで、作業の進捗をリアルタイムで把握でき、手作業によるミスを減らすことができます。
さらに、業務のアウトソーシングやITツールの活用も、業務効率化を進めるための手段です。システム導入により、建設現場の情報や顧客管理のデータを一元管理することができ、より迅速で的確な意思決定が可能になります。
人材育成
建設業界における人材育成は、長期的な経営改善に不可欠です。特に、技術者や現場スタッフのスキルアップは、作業の品質向上や効率化に直結します。効果的な人材育成を進めるためには、定期的な研修や資格取得支援、OJTが有効です。
また、若手社員の育成に力を入れることで、将来的なリーダーを育てることができ、企業の安定的な成長を支えることができます。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるためには、ITスキルを有する人材の育成が重要です。オンライン教育ツールやセミナーを活用することで、効率的に知識を身につけさせることができます。
採用戦略
優れた人材を確保するためには、採用戦略を見直した方が良い場合もあります。現在の人手不足を解消し、企業の成長を支えるためには、採用活動の効率化とターゲット層の見直しを行いましょう。
例えば、求人サイトやSNSを活用して、広範囲に求人情報を配信することが効果的です。また、業界特化型の採用イベントやインターンシップを通じて、建設業に興味のある若手人材を発掘する方法もあります。
さらに、採用後の定着率を高めるためには、労働環境の改善や職場の雰囲気づくりが欠かせません。サポートが充実した環境を整えることで、優秀な人材を長期間にわたって維持することができます。
コスト削減
コスト削減は、企業の利益を確保するために欠かせない施策です。特に、建設業界では原材料費の高騰や人件費の増加が経営を圧迫する要因となります。そのため、購入する資材の選定や仕入れ先の見直しを行い、価格交渉を進めることが重要です。また、エネルギーコストや設備の維持費を削減するために、エネルギー効率の高い設備への投資を行うことも一つの方法です。
さらに、業務のデジタル化によって、無駄な作業の削減や効率化が進み、全体的なコストを抑えることができます。例えば、現場での進捗管理をデジタル化すれば、作業の重複や手戻りを減らすことができ、コストの無駄を防げます。
新規事業
建設業において経営改善を目指すためには、既存事業に依存するだけでなく、新規事業を立ち上げることも重要です。新しいビジネスチャンスを見つけることで、収益源の多角化が図れて、経営の安定性が増すでしょう。
例えば、リフォーム業やエネルギー効率化事業、環境に配慮した建設技術の導入など、今後成長が見込まれる分野に進出することが有効です。
また、建設業に関連する周辺サービスを提供することも新規事業の一つです。設計や施工管理、アフターサービスにも注力するなど、顧客へのサービス範囲を広げることで、より多くの契約を獲得できるでしょう。
リスク管理
建設業界では、自然災害や事故、法規制の変更など、多くのリスクが存在します。これらのリスクに備えるためには、適切な保険加入や、災害発生時の対応マニュアルを整備するなど、リスク管理体制を強化することが重要です。
また、法令遵守に関する教育を定期的に実施し、規制や変更された法律に迅速に対応できる体制を整えることも、リスクを最小限に抑えるために不可欠です。
資金調達
建設業の経営改善には、十分な資金を確保することも重要です。特に、設備投資や新規事業を立ち上げる際には、しっかりとした資金計画を立てることが不可欠。資金調達の方法としては、銀行融資や政府の助成金、クラウドファンディングの利用など、複数の選択肢を検討しましょう。
資金繰りを効率的に行うためには、キャッシュフローの管理を徹底することが重要です。入金・出金のタイミングを把握し、必要に応じて資金を調達できるようにすることで、経営の安定性を保つことができます。
マーケティング
マーケティング戦略を強化することも建設業における経営改善において重要で、特にターゲット市場に対して有効なアプローチを取ることが求められます。オンラインでのプロモーション活動や、SNSを活用したブランディングは、認知度を高めるために非常に効果的です。
また、競合との差別化を図るために、自社の強みや独自性をアピールすることも大切です。品質や納期の確実性、環境への配慮など、顧客が求める価値を提供できることを強調することで、受注の増加が見込めます。
組織改革
組織改革は、経営改善における重要な施策です。特に、組織内での意思決定のスピードを向上させ、従業員のモチベーションを高めることが求められます。フラットな組織を目指し、部署間のコミュニケーションを強化することで、柔軟で迅速な対応が可能になります。
また、部門ごとの役割を明確にし、各スタッフが自分の仕事に責任を持てる環境を作ることも、組織の効率を高めるためには有効です。
事業承継
世代交代を検討している場合、事業承継を進めることも経営改善の一手です。承継計画を立て、段階的に後継者に経営を引き継いでいくことで、企業の安定的な運営が可能となります。
システム導入による建設業の経営改善事例
建設業においても、ITシステムの導入は経営改善の重要な手段として注目されています。特に、施工管理システムや会計・利益管理システムを導入することで、業務の効率化やコスト削減、そして経営の可視化を実現しています。ここでは、原価管理ソフト「要 ~KANAME~」を導入して経営改善を成功させた建設業者の事例を紹介します。
利益管理で売上は最盛期の半分でも利益は2~3倍にUP!
株式会社ケイズエアシステム様は、売上が最盛期の半分にまで落ち込んだにもかかわらず、その後利益が2~3倍に増加しました。これは、「要 ~KANAME~」で利益管理を行ったことで、リアルタイムで利益を可視化できるようになったことが大きな要因です。
具体的には、どの現場が利益を生み出しているか、どこに無駄があるかをすぐに把握できるようになり、そのデータを基に効率的な施策を講じることができました。これにより、無駄なコストが削減され、利益を最大化することができたのです。
また、これまで月単位で管理していた経営状況が、日々の進捗を管理するシステムによって、瞬時に確認できるようになりました。このようなシステム導入により、従業員が自ら利益向上に向けた行動を意識的に取るようになり、利益率が大幅に向上しました。
https://www.pluscad.jp/voice/6063/
会社の「今」を数字で見れるから経営課題に気づけた
株式会社motowa様は、「要 ~KANAME~」を使ってリアルタイムで現場の進捗やコスト、納期などを把握することで、経営者は常に現場の状況を把握し、予期せぬ問題が発生する前に対策を打つことができるようになりました。
以前は、経営者が現場に足を運んだり、各部署から報告を受けたりして、情報を集めていましたが、その方法では時間がかかり、適切なタイミングで対応するのが難しかったのです。システム導入後は、どの作業が遅れているか、予算を超過しているかなど、現場に行かなくても即座に把握できるようになりました。そのため、早期に問題を察知し、適切な対策を講じることが可能になり、結果として経営課題を迅速に解決できるようになりました。
https://www.pluscad.jp/voice/2179/
現場で抜けがちの施工費が見えるようになり、見積りの金額があがった
最後に紹介するのは、株式会社ティープラス様の事例です。この企業では、現場作業で発生するコストを正確に把握できる「要 ~KANAME~」を導入した結果、見積もりの金額が大幅に上がり、利益率も改善されました。
これまで、建設業では現場で発生する実際の施工費用が漏れがちで、正確な見積もりを出すのが困難だったそうです。しかし、システムを導入することで、各工程ごとのコストを自動的に集計できるようになり、過去のデータと比較して適切な見積もりを算出できるようになったのです。この結果、従来の見積もりよりも高い金額で受注を獲得できるようになり、見積もり精度の向上が収益の増加に直結しました。
さらに、このシステムは工事ごとに細かなコスト項目を分けて把握できるため、予算をオーバーしないように細かい管理ができ、無駄な支出を抑制することができたのだそう。このように、システムを活用することで、施工費の管理精度を高め、利益率の向上を実現しました
https://www.pluscad.jp/voice/3432/
まとめ
電気工事業の顧客管理は、業務の効率化や顧客との良好な関係を築くために非常に重要な要素です。顧客情報を適切に管理することで、業務の無駄を省き、サービスの質を向上させ、顧客満足度を高めることができます。システムを導入することで、これらの課題を効率的に解決でき、業務全体の生産性を向上させることが可能です。
また、顧客管理システムを選ぶ際には、その機能の充実度やセキュリティ対策が重要ですが、特に「要 〜KANAME〜」は電気工事業界に特化したシステムであり、現場の管理から顧客情報、請求、アフターサービスまでトータルで提供します。このシステムを導入することで、従業員間での情報共有がスムーズになり、業務の効率化が進むだけでなく、経営状態の見える化が実現できるでしょう。
「要 〜KANAME〜」は、リアルタイムで現場の進捗やコスト状況を管理できるため、プロジェクトの遅延やコストオーバーランの早期発見が可能です。経営者や現場担当者は、常に最新の情報を元に迅速な判断を下すことができるため、結果的に業務の精度が向上し、収益性の改善にも寄与します。
電気工事の顧客管理についてよくある質問
顧客情報をどのように管理するべきか?
顧客情報を適切に管理するためには、まずその情報を一元化できるシステムの導入が必要です。手書きのメモやエクセルで管理している企業も多いですが、顧客情報が増えると管理が煩雑になり、ミスが発生しやすくなります。そのため、CRM(顧客関係管理)システムや、業界に特化した電気工事用の顧客管理システムを導入することをおすすめします。
これにより、顧客の連絡先、施工履歴、過去の請求金額、アフターサービスの履歴などを一元的に管理でき、必要な情報を即座に取り出すことができます。さらに、システムを活用することで、顧客のニーズに応じた対応が可能となり、営業活動の効率化や顧客満足度の向上に繋がります。
顧客情報のセキュリティ対策はどうするべきか?
顧客情報は非常にセンシティブなデータです。そのため、顧客管理システムを導入する際には、セキュリティ対策を十分に考慮する必要があります。情報漏えいや不正アクセスを防ぐために、システムのセキュリティがしっかりと保護されていることを確認しましょう。
具体的には、顧客情報にアクセスできる権限を限定し、従業員ごとにアクセス権限を細かく設定することが重要です。また、データを暗号化して保存することで、万が一データが外部に漏れた場合でも、内容を守ることができます。クラウド型システムを使用する場合には、データセンターのセキュリティ対策がしっかりしているかも確認ポイントとなります。
顧客とのコミュニケーションを効率化する方法は?
顧客との円滑なコミュニケーションは、電気工事業者にとって重要な業務です。特に、現場作業が多いため、顧客と直接連絡を取る機会が限られがちです。こうしたなかで、顧客とのコミュニケーションを効率化するためには、顧客管理システムと連携した連絡手段を活用することが有効です。
たとえば、顧客からの問い合わせや依頼があった場合、その内容をシステムに自動的に記録し、進捗状況や対応状況を共有することができます。また、工事が終わった後にアフターサービスの連絡を一元化して管理することも重要です。自動的に顧客へメールで進捗報告やアフターケアを通知することで、顧客への信頼感が向上し、リピート案件の獲得に繋がります。
さらに、顧客との定期的な連絡をシステムで管理できる機能があると、忘れがちなフォローアップや定期点検を漏れなく実施することができ、顧客満足度を高めることが可能です。
顧客管理において重要なデータはなんですか?
電気工事業の場合、顧客管理で重要なデータは、まず「顧客基本情報」と「施工履歴」です。顧客基本情報には、名前、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)などが含まれ、これらは連絡を取る際に必要不可欠です。
また、施工履歴に関しては、過去にどのような工事を行ったか、いつ工事が行われたか、工事内容に関して特に注意すべき点などの情報が重要です。これにより、次回の工事の際に顧客が以前行った工事内容を把握して、的確な提案をすることができます。
加えて、請求履歴や支払い状況も管理すべき重要な情報です。未払いの請求書があった場合に早期に対処するために、これらの情報をシステムで管理することが非常に有効です。支払い期日や金額をしっかりと管理しておくことで、経営の安定にも寄与します。
顧客管理システムを導入する際のコストはどのくらいか?
顧客管理システムを導入する際のコストは、システムの規模や機能、利用するサポートの内容によって異なります。一般的には、クラウド型システムの月額料金が数千円から数万円程度となっており、規模が大きくなるにつれて料金も高くなる傾向があります。導入に際しては、初期費用が発生する場合もありますが、長期的に見ると効率化による業務改善や顧客管理の精度向上が期待できるため、投資として考えることができます。
ただし、最初に導入した際のコストに加え、運用を続けるうえでの教育やトレーニング費用、システムのカスタマイズ費用なども考慮する必要があります。これらを総合的に見積もり、システム導入後のリターン(業務の効率化や顧客獲得の向上)を踏まえて検討することが大切です。